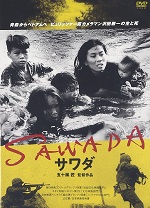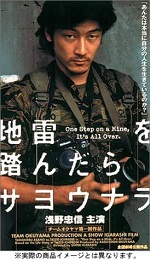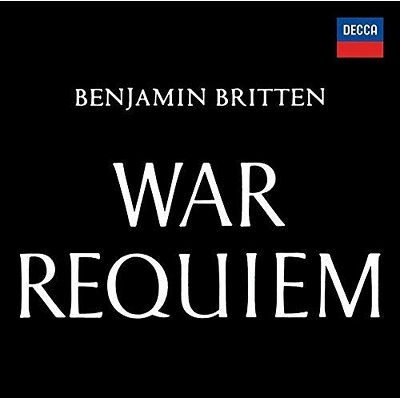
平和主義者ブリテンのメッセージ
英国のベンジャミン・ブリテン(1913~1976年)が1961年に作曲した、管弦楽付きの合唱曲である。レクイエムの原義は、ラテン語で「安息を」という意味で、死者の安息を神に願うカトリックのミサ、死者のためのミサとなり、そこから派生して、ミサに供せられる聖歌となり、現在ではキリスト教の典礼から離れた一般的な「死を悼む曲」や葬送曲まで含むものまでへと広がりを見せている。モーツァルト、ヴェルディ、フォーレのレクイエムが特に有名だが、ベルリオーズ、ブラームス、ドヴォルザークなど、数多くの作曲家が手がけているのも、追悼と癒しをもたらす宗教と、そのための場としての教会、そこに求められたのが音楽だったということなのかもしれない。
数あるレクイエムの中で、とりわけこの曲がユニークなのは、単に死者の安息を祈るのではなく、明確に第二次大戦による全ての国の犠牲者を追悼する曲だという点だ。フル・オーケストラと室内管弦楽団の二つを背景に、ソプラノ、テノール、バリトンの三人の独唱者、混声八部合唱および児童合唱という大規模な編成を必要とする壮大な作品で、歌詞は、ラテン語のカトリック典礼文のほか、第一次大戦に従軍し、25歳で戦死した英国の詩人ウィルフレッド・オーウェン(1893~1918年)による英語の詩が使われている。そう、この大曲は、戦争の不条理を告発し、恒久の世界平和を願う、ブリテンの魂の叫びなのだ。
空襲で破壊されたコヴェントリーの聖マイケル大聖堂。1958年、その再建を祝う献堂式に供される楽曲を委嘱されたブリテンは、戦争で対峙し、甚大な被害をこうむった双方の交戦国の歌手を独唱者とすることを、当初から念頭においていた。それがソ連のソプラノ、ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(1926~2012年)、英国のテノール、ピーター・ピアーズ(1910~86年)、ドイツのバリトン、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(1925~2012年)である。三人は快諾したが、当時は米ソを盟主とする東西冷戦体制下、1962年のメレディス・デイヴィスが指揮するバーミンガム市交響楽団による初演に、ヴィシネフスカヤだけは参加することができず、英国のヘザー・ハーパーがソプラノをつとめた。
初演に先立つ四ヶ月も前のこと、当時のデッカ・レコードのプロデューサーだったジョン・カルショー(1924~80年)は、スコアから作品のすばらしさを一目で見抜き、録音を決意。翌1963年のレコーディングにはヴィシネフスカヤも加わることができた。半世紀以上も前の録音であるが、今なお当演奏の代表盤とされる、それがこのCDである。
戦争を題材にした小説、詩、絵画、写真、芝居、映画、そして音楽…。そういうものは、確かにある。しかし、銃弾の飛び交う中や空襲のもとで、それを描くことは無理だ。文学も芸術も、平和だからこそ可能なのである。アーティストやミュージシャンが平和のために闘う理由は、まさにそこにあるのだろう。
指揮:ベンジャミン・ブリテン
演奏:ロンドン交響楽団
独唱:ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(ソプラノ)
ピーター・ピアーズ(テノール)
ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)
合唱:ロンドン交響楽団合唱団、ハイゲート学校合唱団
録音:1963年
(しみずたけと) 2021.8.17
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ