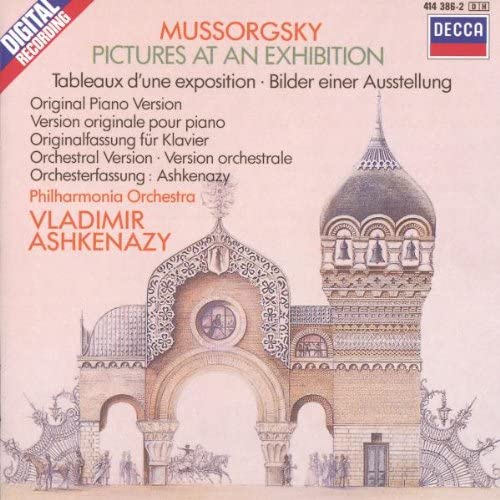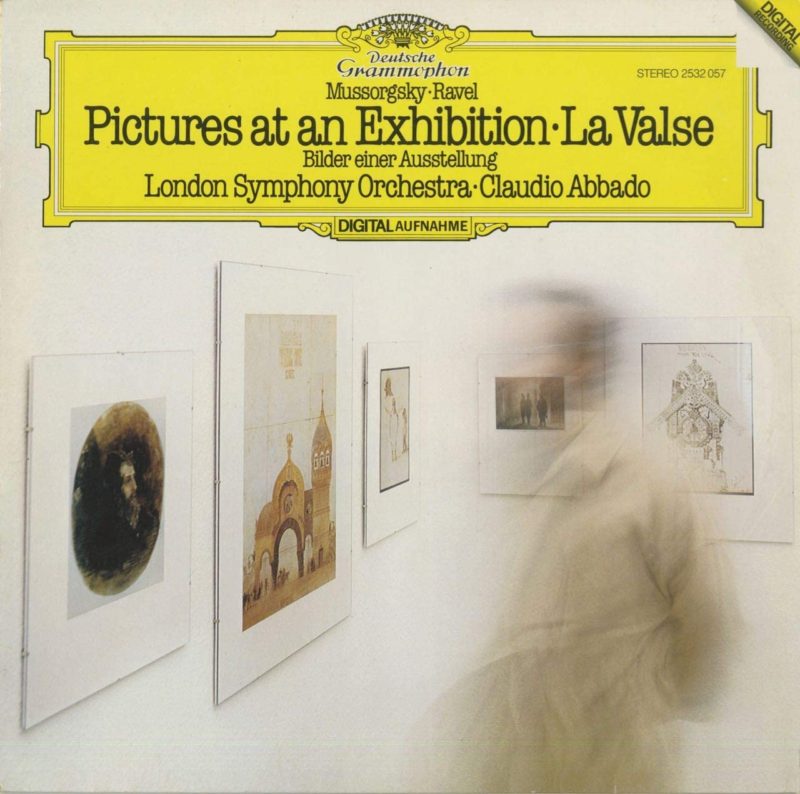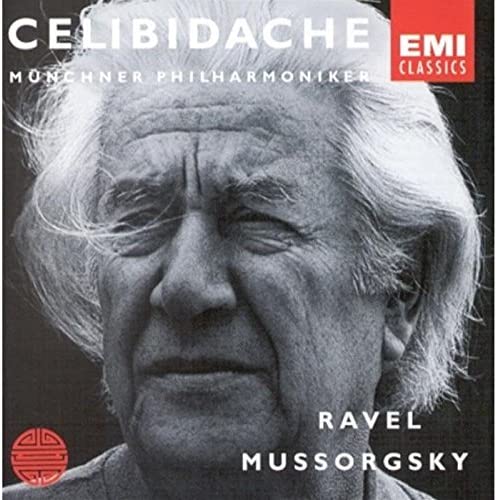Carol of the Bells
鐘のキャロル
12月も半ばとなり、クリスマスの音楽を聴くのが楽しい。
音楽用語にオスティナート(伊:ostinato)というのがあると知った。あるリズム、メロディ、または和音が何度も反復されることを指す。ことばの意味は「執拗な」とのこと。
「執拗な」というだけあって、オスティナートは強く印象に残る。「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」というクリスマス・ソングを初めて聴いた時にもそうだった。下の譜面からわかるように、こんなふうに反復されている。

Wikipediaをのぞいてみた。「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」はウクライナ人のマイコラ・レオントーヴィッチュ(Mykola Leontovych 1877-1921)が「シュチェドルィック」Shchedryk というウクライナの民謡をベースに1916年に編曲して作り上げたものである。「シュチェドルィック」はウクライナのことばで「豊富な、潤沢な」という意味、キリスト教以前の時代には春を祝う4月の歌だった。今年の豊作と家族の幸せを願った歌だ。キリスト教がもたらされ、ユリウス暦が採用されたことによって、暦が移動し、1月に新年を祝う歌になったのだとか。
では、なぜ新年を祝う歌がクリスマス・ソングになったのだろうか。アメリカ人作曲家のピーター・J・ウィルウフスキー (Peter J. Wilhousky 1902-1978)が1936年に、民謡で歌われる意味とは異なった英語の歌詞を付けてクリスマスの音楽とし、アメリカやカナダで特に好まれて歌われたよし。
オスティナートがゆえに人々の印象に残るのか、あらゆるジャンルの音楽で、世界中の多くの歌い手や演奏者が「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」を演奏している。それぞれたいそう異なっていて、これが良いよー!とは言えないのがつらいけれど、三つほど紹介したい。(わたしがたまたま耳にした曲というに過ぎないけれど。)
まず初めに紹介するのは「キトカ」 KITKAという、アメリカ、オークランドの女声合唱グループが歌うキャロル・オブ・ザ・ベルズ。キトカは東ヨーロッパの民謡を歌うグループとのこと。東ヨーロッパではしばしば正調で歌われる合唱を耳にする。とは言っても、「正調」ということばの意味は今ひとつわからない。辞書には民謡などで伝統的な歌い方をする場合に用いられるとあるが、わたしは昔からこのことばを発声方法にあてはめて自己流に使ってきた。日本の民謡でも「正調そーらん節」といった使われ方をするようだけれど、その意味もよくわからない。他の音楽ジャンルによるアレンジなしの演奏ということだろうか。英語では、Traditional tune などという。キトカも正調で歌うグループではあるけれど、このシュチェドルィックではそれは顕著ではない。
正調で歌う合唱は一般にブルガリアン・ヴォイスといわれるのだろうか。Cosmic Voices from Bulgaria だとか、Bulgarian Voices というブルガリアの合唱グループが音楽検索で浮かび上がってくる。東欧には数えきれないほどの民謡の合唱グループがあることだろう。ダンスも豊富で魅力的な地域だ。
次に挙げるのはこの曲を世界に広めた元祖、スウィングル・シンガーズ Swingle Singersかなと思ったけれど、クリスマスの歌といえば、リベラの歌が思い浮かぶ。わたしが子どもの頃はウィーン少年合唱団だったけれど。リベラの合唱は他とは少々異なったアレンジが美しい。
次はジャズ・バージョン。デイヴィッド・ベノワのピアノ・ソロ。わたしの、なかなかのお気に入りである。彼のトリオ・バンド版もあるけれど、ソロはとても良い。このアルバムは2020年にリリースされた。『ピーナッツ』の絵が使われているのは、1989年に『ピーナッツ』の生誕40周年に寄せたコンピレーション・アルバムに参加して以来の縁らしい。
ケルン大聖堂の鐘たち
さてさて、話はガラッと変わり、正真正銘の『キャロル・オブ・ザ・ベルズ』のこと、ケルン大聖堂の鐘たちである。まずは、その鐘の音を下の動画で数分間だけでも聴いてほしい(動画は30分間)。2012.12.7の撮影とある。クリスマス・バージョンの鐘の音かもしれない。
最初の10分間は一番大きいベルが鳴るのみなので、ここでは13分31秒、隣りのより高音のベルが振れ始める直前から聴けるようにした。初めの10分間は大きいベルの独演というわけだ。撮影カメラの位置が変わるため、確実には数えることができないものの、5つほどの大小のベルが同時に振れるのを見ることができる。低音から高音までの複数のベルが鳴り、クライマックスが過ぎ、やがて高音のベルから徐々に止まっていく。動画の28分頃には一番大きいベルのみの音となり、それも1分間ほどで静止する。
ケルン大聖堂の塔はツインになっていて、南塔に備わっている大小8つのベルがメインとなって市中に鐘を鳴り響かせている。真ん中の一番大きいベルは「太っちょペーターさん」との愛称があり、重量は24トン、直径は3.22メートル、1923年に鋳造された。先代のベルは1875年に設置されたばかりだったが、1908年に鐘舌が落ちてしまい、第一次世界大戦に用いるために1918年、溶融された。1924年からは現在の「太っちょペーターさん」が鳴っている。8つのベルの中で一番若い。今年98歳ではあるけれど。
ペーターの次に大きなベルは1448年設置のPretiosaと1449年設置のSpeciosa、直径がそれぞれ2.4メートル、2.03メートル。中世後期から鳴り響いているということか。気が遠くなる。
(Ak.) 2022.12.13
関連記事へ跳ぶ : Church Bells of England
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ