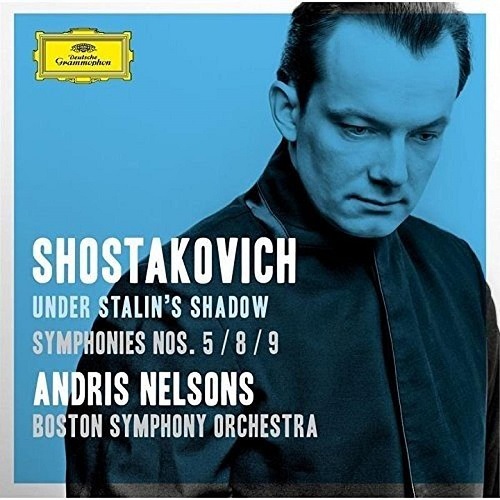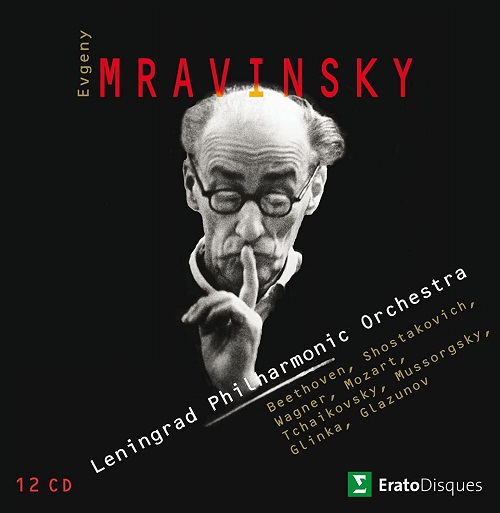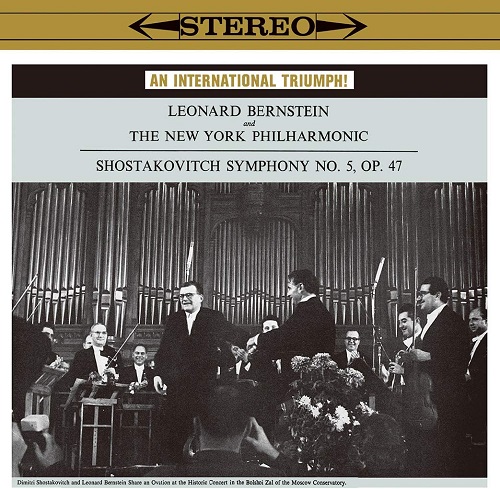ドミートリイ・ショスタコーヴィチ
交響曲第7番『レニングラード』
交響曲第8番
「ドミートリイ・ショスタコーヴィチ(1906~75年)の交響曲第7番、第8番、第9番は大祖国戦争を背景に作られた。それゆえ、この3曲を一括りにして「戦争交響曲」と呼んだりする。前回、第9番を紹介する中で、第7番と第8番にも少しだけ触れたのだが、このサイトの《みました!》に映画『戦争と女の顔』が出たので、ここで書いておくことにした。そう、交響曲第7番はレニングラード包囲戦の下でつくられ、その戦闘によって荒廃した街を舞台にしているのが、この『戦争と女の顔』だからである。
交響曲第7番『レニングラード』
交響曲第5番の成功で、プラウダ批判で受けたダメージを一気に回復したショスタコーヴィチであったが、つづく第6番の評価はパッとしなかった。まあ、当時のソ連では、音楽作品としての出来不出来より、政治的な動機、つまり国家をヨイショするものであるか否かで左右される傾向が強かったので、本当の音楽好きとしては、そうした政治的背景が影を落とす評価など気にすることもあるまい。
ナチス・ドイツとソ連邦は、1939年8月23日、「独ソ不可侵条約」を結んだ。署名した両国外相の名をとり、モロトフ=リッベントロップ協定とも呼ばれる。39年9月1日にドイツがポーランドに侵攻し、ポーランドの同盟国だった英仏が宣戦布告したことで第一次大戦が勃発した。すかさずソ連も17日にポーランド領内に侵攻。ドイツとソ連は、独ソによるポーランド分割、ソ連のバルト三国併合とフィンランド侵攻を、秘密協定で相互に承認していたのである。
41年6月22日、ドイツ軍はバルバロッサ作戦でソ連に侵入し、ここに独ソ戦の火ぶたが切られた。9月、ロシア革命の父レーニンに因んで改名された古都ペテルブルクがドイツ軍に包囲される。ヒトラーがレニングラード攻略を思い立ったのは、「イデオロギー戦」が理由だったのか、あるいは文化の中心を掌握することで、ロシア国民の戦意を挫こうとしたのか。ショスタコーヴィチは人民義勇軍に入ることを望んだが、偉大な作曲家を失っては一大事と、友人らが手を回し、戦闘に直接関わらないですむ民間消防団の一員として、音楽院の屋上で防空監視する役目に就く。街をめぐる攻防戦は、約900日にもわたるのだが、それを目の当たりにし、この第7番は極めて短い時間で書き上げられた(ことになっている)。
ショスタコーヴィチは、曲の発表にあたって、「これは闘いの詩であり、根強い民族精神への賛歌である」と述べたと言う。第1楽章は戦争、第2楽章は回想、第3楽章は祖国の広野、第4楽章は勝利とされ、演奏時間は約75分にも及ぶ長大な曲であるが、戦争の主題や侵略の主題、人間の主題が次々にあらわれ、むしろ標題音楽とも呼べそうな性格である。ソ連政府は、あらゆる芸術を大祖国戦争に動員したわけであるから、この曲もまたソ連のプロパガンダと無縁だとは言い切れない。
当時、中央政府はモスクワからクイビシェフに退避しており、ここでなされた初演は、まるで政治報道かのようにラジオ放送でソ連中に伝えられ、これを聴いた国民は熱狂した。さらに戦火の中にあるレニングラードでも演奏され、市民を勇気づけることになる。しかし…。
しかし、ソロモン・ヴォルコフによる《ショスタコーヴィチの証言》の中で、ショスタコーヴィチはこの曲を、「第7交響曲は戦争の始まる前に構想されていたので、したがって、ヒトラーの攻撃に対する反応として見るのはまったく不可能である。『侵略の主題』は実際の侵略とはまったく関係がない。この主題を作曲したとき、私は人間性に対する別の敵のことを考えていた」と述べている。第7交響曲は、戦火のレニングラードで作られたのではなかったのか?人間性に対する別の敵とは、いったい?
ショスタコーヴィチが語ったとされる「当然、ファシズムは私に嫌悪を催させるが、ドイツ・ファシズムのみならず、いかなる形態のファシズムも不愉快である。今日、人々は戦前の時期をのどかな時代として思い出すのを好み、ヒトラーがわが国に攻めてくるまでは、すべてが良かったと語っている。ヒトラーが犯罪者であることははっきりしているが、しかし、スターリンだって犯罪者なのだ」という箇所から、スターリンもまたファシストであり、人間性に対する敵と見なしていることがわかる。
スターリンを、ヒトラーと同等、いやそれ以上の悪と捉えているかのような証言が続く。「ヒトラーによって殺された人々に対して、私は果てしない心の痛みを覚えるが、スターリンの命令で非業の死をとげた人々に対しては、それにもまして心の痛みを覚えずにはいられない。拷問にかけられたり、銃殺されたり、餓死したすべての人々を思うと、私は胸がかきむしらられる。ヒトラーとの戦争が始まる前に、わが国にはそのような人がすでに何百万といたのである」からは、かつて自分にもそのような危機が迫り、幸運にも生き延びることができたという、苦しい記憶があるのだろう。
《ショスタコーヴィチの証言》を偽書とする説もある。しかし、作曲家ショスタコーヴィチに向けられた様々な圧力、それに起因する彼の苦悩、そして国外に亡命した多くの芸術家のことを思うと、言葉の一字一句まで正しいとは言えないにしても、「第7番が《レニングラード交響曲》と呼ばれるのに私は反対しないが、それは包囲下のレニングラードではなく、スターリンが破壊し、ヒトラーがとどめの一撃を加えたレニングラードのことを主題にしていたのである。私の交響曲の大多数は墓碑である」という作曲家の言葉を、私は虚偽であるとは言い切ることができない。
交響曲第8番
独ソ戦は二年が過ぎ、ドイツ軍はカスピ海とコーカサスの油田を狙ってソ連で第二次大攻勢を展開。パウルス将軍率いる第6軍は、世紀の大激戦地となるスターリングラードを目指した。ヒトラーは、ソ連の指導者の名を冠するこの街を、何が何でもたたきつぶしたかったのだろう。交響曲第7番の二年後、この第8番は作られた。
この曲が発表されたとき、ショスタコーヴィチは次のように述べている。「交響曲の内容を正確に叙述することは至難である。第8交響曲の内容の根本にある思想をごく短い言葉で言いあらわすのならば、『人生は楽し』である。暗い陰うつなものはすべて崩れ去り、美しい人生が今や開かれつつある…」と。
反撃に出たソ連軍により、スターリングラードでドイツ軍が壊滅した。翌年1月にはレニングラードの包囲も解かれる。防戦一方だった戦争にも、明るい兆しが見え始めたのである。スターリングラードは、独ソ戦の一大転換点だった。ドイツ軍を敗走させ、ソ連軍が攻勢に転じた時期に作曲された第8番は、一時期、《スターリングラード交響曲》とも呼ばれたりした。
第8番は、第7番とはうって変わり、標題音楽ではない。しかし、作曲家の言葉と裏腹に、第1楽章の重苦しいアダージョだけで、全曲の約半分にもならんとする。第1楽章が第1部で、それ以後の楽章が第2部を構成しているようで、ある意味、バランスが良いとは言えない。おどけるような第2・第3楽章の後に展開される第4楽章のラルゴもまた重く、そして暗い。「人生は楽し」と感じさせるような楽観的な要素は、いったいどこにあるというのだろう。
スターリングラードの街は瓦礫の山と化し、軍民多くの犠牲を出した。現実は楽しいどころではなかったはずである。希望があったとすれば、侵略を阻止し、目の前の苦しさから不死鳥のごとく立ちあがろうとする人々の「生の追求」だったのか。ショスタコーヴィチの言葉は、「芸術は楽観主義的・人生肯定的なものでなければならない」という当局の要請である社会主義リアリズムに沿って、やむなく語られたものだったように思える。
ショスタコーヴィチは、スターリングラード攻防戦を叙事的に描いたのではなく、戦争の時代に生きた、生きざるをえなかった人々を主題に、戦争の悲惨さ、鎮魂、人間のあり方や生き様を問いかけたのである。その意味では、歴史的外観を描いた第7と人間の心を描いた第8の二つの交響曲は、背中合わせの関係とも言えよう。
この曲が発表されたとき、反革命的で反ソビエト的だと公然と宣告されたそうである。《ショスタコーヴィチの証言》によれば、「戦争の初期には楽天的な交響曲を書いていたのに、いま、悲劇的なものをかいているのはなぜか。開戦当初、我々は退却しつつあったが、今や攻勢に転じ、ファシストを壊滅しつつある。ショスタコーヴィチがいま悲劇的なものを書き始めているのは、彼がファシストの味方であることを意味する…」と。ほとんど言いがかりでしかない。しかし、それこそが全体主義が生み出す空気なのであろう。これが言いがかりにすぎないことを看破できるのは、私たちがその集団の外にいるからである。中に入ってしまうと気づかない、見えない、わかっても声を出せない…。あの時代のソ連だけではない。それは、私たちのすぐ隣にある恐ろしい事実なのだ。
::: CD :::
交響曲第7番『レニングラード』

指揮:ヴァシリー・ペトレンコ
演奏:ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
録音:2012年
1976年、レニングラード(現サンクトペテルブルク)に生まれたヴァシリー・ペトレンコ。作曲者と同郷の彼がロイヤル・リヴァプール・フィルを振った演奏。ペトレンコの手によって、この楽団は一気に世界の檜舞台の躍り出たと言って良いだろう。2008年から5年をかけて制作されたショスタコーヴィチ交響曲全集の中でも、この第7番は特に素晴らしい。長大な曲であるにもかかわらず、滑らかに流れ、シャープな響きと相まって、緊張と集中が途切れることがないまま、スケールの大きなクライマックスに至り、圧倒される。
ペトレンコは、ロシアのウクライナ侵攻を理由に、2021年に就任したロシア国立交響楽団を辞任している。「ロシアとウクライナの人々の間には歴史的および文化的なつながりがあり、ロシアの侵略を正当化する理由はどこにもなく、今起こっている悲劇は、今世紀最大の道徳的失敗と人道的災害の一つです。これらの恐ろしい出来事に応え、私は平和が回復するまでロシアでの仕事を中断することに決めました」と、芸術家としてプーチン体制に与しない立ち位置を明確にしたと言えよう。
交響曲第8番
この曲は、高く評価はされているものの、第5番や第7番ほど録音されていない。まず思い浮かぶのは、1982年のムラヴィンスキーとレニングラード・フィルのライブ盤だ。初演者だけあって、息苦しさをおぼえるほどの緊張感に終始し、オーケストラのアンサンブルも完璧。ソ連時代、実質的に演奏が禁じられていたことも影響しているのだろうか。
ムラヴィンスキーの音楽は見事なのだが、あの時代、彼はショスタコーヴィチに圧力をかけた権力、その中枢から遠からぬところにいた人物である。ここでは、そうした全体主義を外から俯瞰できる、そういう立ち位置にある者による演奏をとりあげたい。

指揮: アンドレ・プレヴィン
演奏: ロンドン交響楽団
録音: 1992年
残忍で冷徹な体制に対して、人は人としての矜持と尊厳を失うことなく対峙できるか。まさにこの問いかけこそが、ショスタコーヴィチの交響曲を貫く思想である。第8番は、全体主義の至るところに仕掛けられた罠をすり抜けるための迷路の中で、自分を生かす、生き延びるための道を見出そうとするように始まる。それが困難な社会であるからこそ、第1楽章はあれほど長いのだ。
おどけのような第2、第3楽章は、軽薄短小なピエロを演じることで権力の目を欺き、逃れようとする作曲者自身であろうか。しかし、それもまた虚しいことだ。第4楽章は、そんな諦観か、あるいは悟りを思わせる。そして最終楽章。平和への願望は、はかなさを感じさせながら終わっていく。
プレヴィンの知的で暖かみのある人間的な音楽は、ショスタコーヴィチの矜持と悲観を共有するところから生まれている。それは作曲家への慰め、励まし、そして最後には人間の内心が勝利することへの確信であろう。この演奏の最大の魅力は、血が通ったものであるところにある。
(しみずたけと) 2022.8.12
ショスタコーヴィチ : 交響曲第10番 記事へ
ショスタコーヴィチ : 交響曲第5番 記事へ
ショスタコーヴィチ : 交響曲第9番 記事へ
ショスタコーヴィチ の「戦争交響曲」 7番 8番 記事へ
抵抗するショスタコーヴィチ 4番 13番 この記事
ショスタコーヴィチ : 交響曲第14番『死者の歌』 記事へ
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ