別所憲法9条の会 《9j音楽ライブラリー》へリンク
ビッグ・ファイブ。クラシック音楽の話の中で、この名称にピンとくるのは、おそらく戦後生まれの昭和世代くらいだろう。この言葉が使われるようになったのは、レコードへの長時間録音が可能になり、オーケストラの演奏会がラジオ放送のレギュラー番組として拡大していった1950年代あたりだからである。
米国では、早くから東海岸が政治や経済の中心地として発達し、また欧州文化の入口でもあったため、歴史を持つオーケストラが東海岸に偏在することになったのは当然の成りゆきだったろう。最も古いニューヨーク・フィルハーモニックが1842年、ボストン交響楽団は1881年、フィラデルフィア管弦楽団は1900年の創立である。これらをビッグ・スリーと称していたのだが、20世紀中頃にめきめきと力をつけ、頭角を現してきたのが、フリッツ・ライナー率いるシカゴ交響楽団(1891年創立)とジョージ・セルのクリーブランド管弦楽団(1918年創立)。これらがラジオ放送やレコードで耳目を集める存在となり、ビッグ・ファイブ、すなわち全米五大オーケストラと呼ばれるようになったのである。
経済基盤が豊かになった地方の中核都市でも、野球やフットボール、バスケットボールのチームが活躍するのと同様、“おらが町のオーケストラ”の実力が向上、知名度を上げるにつれ、エリート・イレブンなる呼称も現れた。それでは実力と人気を兼ね備えたビッグ・ファイブ以外のオーケストラはどれくらいあるのだろうか。主だったものを創立順に並べてみると、
セントルイス交響楽団(1880年)
ピッツバーグ交響楽団(1895年)
ダラス交響楽団(1900年)
ミネアポリス交響楽団(1903年、現ミネソタ管弦楽団)
サンフランシスコ交響楽団(1911年)
ヒューストン交響楽団(1913年)
デトロイト交響楽団(1914年)
ボルティモア交響楽団(1916年)
ロサンゼルス・フィルハーモニック(1919年)
ワシントン・ナショナル交響楽団(1931年)
アトランタ交響楽団(1945年)
などであろうか。ヨーロッパにくらべて浅い歴史しか持たない新興国アメリカのオーケストラだが、その多くが百年を超える歴史を持つことに驚かされるのではないだろうか。もちろん、これらの中には不況や戦争などの理由で活動を休止していた時期があったり、経営難に陥った後に再建されたものも含まれているのだが、今日なお精力的に演奏活動を続ける、世界的にも名門と呼ぶのに相応しいオーケストラであることには違いない。
このように、各地にオーケストラが作られた背景には、国土が広く、演奏家の長距離移動が容易でなかったことがある。米国の大学に、日本のようにいくつもの大学を掛け持ちする非常勤教員がほとんどいないのも同じ理由であろう。大学教員の事情はさておき、近年、飛行機を路線バスのように利用することが普通になったこともあり、こうした問題は解消に向かいつつある。さらにはレコード会社の再編(レーベルの統廃合)が進み、音楽配信が普及したことにより、オーケストラがレコード会社と契約を結ばず、オーケストラ独自で録音・販売する自主レーベルも珍しくなくなった。こうしたことが重なり、オーケストラの歴史的名声の意味が薄れてきたのも事実である。演奏家も、どのオーケストラに所属するかを決める際、ひたすら名門を求めて渡り歩くよりも、労働環境、住みやすい町、子どもの教育など生活環境を重視する傾向が見られるようになった。音楽は手についた職の一種であるから、彼ら・彼女らは世界中のどこにでも行くことができる。
とはいえ、音楽家が活動拠点を移すのは今に始まったことではない。大規模な人の移動は、欧州の植民地獲得競争の時代に始まり、それは帝国主義の時代に全世界へと広がった。とりわけ19世紀のポグロム、20世紀のホロコーストと、反ユダヤ主義が吹き荒れる中、多くのユダヤ人が移民、難民と化した。彼ら・彼女らが移住先に選んだのが“人種のるつぼ”であるアメリカ合衆国だったのである。
しかし、アメリカは溶け合うことで皆を均質化する坩堝(るつぼ)などではなかった。むしろ公民権運動を経た1970年代以降は、それぞれの文化を尊重し合う多文化主義こそがアメリカ的であるという考えが主流となり、“サラダボウル”であると言われるようになる。サラダボウルの中で、ベーコンはベーコン、レタスはレタス、トマトはトマト、溶け合ったりせず、それぞれがベーコンやレタス、トマトとして自己主張しながら一緒に存在するというわけである。トランプ以後、ベーコンとレタス、トマトの共存はどうなるのか、米国社会がどこに向かうのか、気になるところではある。具材が一種類のサラダなど、美味しいはずがないし、そんなものはサラダとは呼べない、いや料理ですらない。
話をオーケストラに戻そう。LPレコードとラジオ放送が普及する20世紀半ば、それはビッグ・ファイブを頂点とする米国のオーケストラが、独墺や英仏などのクラシック音楽の伝統国のそれに一歩も引けをとらない地位を築き上げた時代なのだった。いったいそれは誰の功績であるのか、オーケストラごとに振り返ってみたいと思う。
1.ニューヨーク・フィルハーモニック
まずは最も歴史の古いニューヨーク・フィルハーモニック。1448年のデンマーク王立管弦楽団、1548年のシュターツカペレ・ドレスデン、1743年のライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団には及ばないものの、あのウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と同じ1842年の創立である。
1951年から57年まで音楽監督を務めたのはギリシャ人のディミトリ・ミトロプーロス(1896~1960年)。彼の指揮者としてのキャリアは、1922年、ベルリン国立歌劇場の助手に始まったと言って良いだろう。上司にあたる第一指揮者のフリッツ・シュティードリー(1883~1968年)はマーラーの弟子で、アルノルト・シェーンベルク(1874~1951年)の仲間でもあった。ミトロプーロスが早くから熱心にマーラーと新ウィーン楽派の作品に取り組んでいたのは、シュティードリーの影響であるのは間違いない。同じ時期、ジョージ・セルも同楽団にいたのであるが、シュティードリーは二人を「昼と夜ほども違う」と評した。冷静でアポロ的なセルに対し、情熱的なミトロプーロスをディニオニソスに喩えているのだが、確かにミトロプーロスのマーラーは熱く、その解釈は、後にレナード・バーンスタイン(1918~90年)など多くの指揮者に影響を与えることになった。
1946年、ミトロプーロスは米国籍を取得。ミトロプーロスの後にニューヨーク・フィルハーモニックの音楽監督に就任するのがバーンスタインなのだが、彼がウクライナ系移民の二世であることは、《平和の闘士バーンスタイン》の中で書いたとおりである。
2.ボストン交響楽団
1949年から62年にわたってボストン交響楽団を率いたのが、ドイツ帝国領アルザスに生まれ、後にフランスに帰化したシャルル・ミュンシュ(1891~1968年)だ。アルザスは、普仏戦争でドイツ領になり、第一次大戦後はフランスになるなど、国家間の戦争に翻弄された土地である。彼はドイツ生まれのフランス人か、それともフランスで活躍したドイツ人なのか。○○人という呼称に何の意味があるのか、今いちど問い直してみるのが良さそうだ。その彼が米国のオーケストラにフランス的な香りと情熱を持ち込んだ。ミュンシュが退任した後を引き継ぎ、1969年まで音楽監督を務めたのがエーリヒ・ラインスドルフ(1912~93年)である。
ウィーンのユダヤ人家庭に生まれたラインスドルフは、ザルツブルク音楽祭でブルーノ・ワルター(1876~1962年)とアルトゥーロ・トスカニーニ(1867~1957年)のアシスタントを務めるなど、着々とキャリアを積み上げた。1937年11月にメトロポリタン歌劇場のアシスタント指揮者に就任するために渡米。その四ヶ月後、オーストリアはナチス・ドイツに占領された。ユダヤ系の彼は帰る場所を失う。42年、後に大統領となる下院議員リンドン・ジョンソンの支援によって、彼は米国の市民権を取得した。
オペラ指揮者としても、ヴェルディの『アイーダ』、プッチーニの『蝶々夫人』、リヒャルト・シュトラウスの『サロメ』、そしてワーグナーの『ローエングリン』や『ワルキューレ』などの全曲盤は高い評価を得ている。1962年に音楽監督に就任したボストン響はコンサート・オーケストラなので、オペラ上演からは遠ざかったが、この楽団にマーラーやプロコフィエフを定着させた功績は大きい。
ラインスドルフを継いだのは、やはりユダヤ系ドイツ人で、ピッツバーグ交響楽団と兼任のウィリアム・スタインバーグ(1899~1978年)。1972年までの三年間だった。その後が小澤征爾(1935~2024年)なのだが、73年から2002年までという、ボストン響の歴代指揮者の中で最も在任期間の長い音楽監督となった。フランス音楽を得意としたミュンシュ時代のボストン響は、強靱だが決して重厚ではない、軽く美しい音色を特色とする弦セクションだったのだが、小澤征爾はこれをドイツ的な重い音へと変えさせた。おそらくマーラー演奏のためだったのであろう。それは見事に成功したのだが、これは小澤征爾ひとりの手柄ではない。ボストン響のグスタフ・マーラー(1860~1911年)への傾倒はラインスドルフによって既に先鞭がつけられていたのである。
3.フィラデルフィア管弦楽団
フィラデルフィア管弦楽団が世に知られるようになったのは、音の魔術師と言われたレオポルド・ストコフスキー(1882~1977年)によってであろう。ポーランド移民の父とアイルランド人の母の間に英国ロンドンに生まれた彼は、1912年にフィラデルフィア管弦楽団の常任指揮者に就き、同楽団のアンサンブルを世界一流にまで育て上げた。ストコフスキーとフィラデルフィア管弦楽団のコンビは、1937年の映画『オーケストラの少女』と1940年のディズニー映画『ファンタジア』が世界中で上映されたこともあり、その名を不動のものとしたのである。
ストコフスキーの後を受けたのが、ハンガリーからの移民ユージン・オーマンディ(1899~1985年)。元々はバイオリニストであった。1921年に渡米し、ニューヨーク・キャピトル劇場のオーケストラでバイオリンを弾くようになったのだが、23年にはコンサートマスターに。翌年、急病で倒れた指揮者の代役を務め、それをきっかけに指揮者へと転向した。31年、これもまた急病のトスカニーニに代わって指揮をしたフィラデルフィア管弦楽団の公演が成功し、ミネアポリス交響楽団(現ミネソタ管弦楽団)の常任指揮者に、36年にはフィラデルフィア管弦楽団の共同指揮者をストコフスキーと分け合うまでになった。
1938年、ストコフスキーの辞任により音楽監督に就いたオーマンディは、80年に勇退するまでの42年間の長きにわたってフィラデルフィア管弦楽団に君臨。バイオリン奏者だったこともあり、彼は弦楽セクションを中心に据え、きらびやかではあるが落ち着きのある、磨きぬかれた音づくりが一番の特色であろう。優秀な演奏家を集め、世界で一番多くのストラディバリを保有するゴージャスな音、人々はそれをフィラデルフィア・サウンドと呼んだ。なお、27年に米国籍を取得したオーマンディは、ハンガリー生まれのアメリカ人ということになる。
4.シカゴ交響楽団
今や押しも押されもせぬ世界最高峰のオーケストラの一つのシカゴ響。ヴィルトゥオーソ・オーケストラとして認められるようになったのは、1953年に第六代音楽監督として就任したフリッツ・ライナー(1888~1963年)の手腕に負うところが大きい。そのあまりの厳しさは、楽団員の労働環境としてはいささか疑問でもあるのだが、彼なくして同楽団が世界のトップに躍り出ることはなかっただろう。
ライナーはハンガリーのブダペストに生まれた。ライバッハ(現スロベニアの首都リュブリャナ)の歌劇場を皮切りに、ハンガリーやドイツのオーケストラ、歌劇場で指揮をする。1922年に渡米、帰化して米国市民に。シカゴ響に就任する前はシンシナティ交響楽団、ピッツバーグ交響楽団の音楽監督を務めたたほか、メトロポリタン歌劇場でも指揮をした。バーンスタインはカーティス音楽院指揮科教授時代の教え子である。
1962年までのライナー時代をシカゴ響の第一期黄金時代と呼ぶなら、第二期はゲオルク・ショルティ(1912~97年)が第八代音楽監督を務めた69年から91年であろう。ショルティもまたハンガリー人で、後に英国籍を取得している。
5.クリーブランド管弦楽団
短い期間ではあったが、クリーブランド管弦楽団の本拠地であるセヴェランス・ホールから遠からぬところで暮らしていたこともあって、私にとってこのオーケストラは特に思い出深いものだ。
地方オーケストラにすぎなかった同楽団を全米有数の楽団に仕立て上げたのはジョージ・セル(1897~1970年)。ハンガリーのブダペストに生まれた彼だが、三歳の時に一家揃ってユダヤ教からカトリックに改宗した。ナチの脅威から逃れるために英国に活動拠点を置いたが、米国での演奏旅行中に第二次大戦が勃発、そのまま留まることに。1946年、アメリカ国籍を得たセルはクリーブランド管弦楽団の音楽監督に就いた。彼は音楽監督というだけでなく、人事を含むあらゆるマネージメントの権限を手に入れ、大鉈を振るう。最初のシーズンが終わるときには楽団員の三分の二が入れ替わっていた。徹底的な練習を積み重ね、「セルの楽器」と言われるまでに精緻な、世界最高のアンサンブル能力を発揮するまでになる。理論的であまりにもな完璧さであるがゆえに「冷たい」という評価もあるが、感情に流されない理知的な音楽であるとも言えよう。このあたりは聴く人の嗜好にもよるところだ。1970年に手兵のクリーブランド管弦楽団を引き連れて来日。大阪万博で演奏したときは、会場が野外だったため、風が吹いてティンパニのピッチが狂い、それがもとでアンサンブルが総崩れになった。
ハプスブルク家の支配下にあったハンガリー生まれゆえ、同郷のバルトークやコダーイ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームスなどの独墺系が素晴らしいのはもちろんだが、ドヴォルザークやチャイコフスキー、ムソルグスキーなどの国民楽派の作品には「暖かみ」さえ感じさせてくれる。
もうおわかりだろう。ニューヨーク・フィルハーモニック、ボストン響、フィラデルフィア管弦楽団、シカゴ響、クリーブランド管弦楽団をビッグ・ファイブに押し上げたのは移民、移民の二世、三世、外国人の指揮者たちの力によるものであることが。ビッグ・ファイブだけではない。他のオーケストラも同様だ。指揮者だけでもない。楽団員にはたくさんの移民やその子孫、外国人がいる。彼ら・彼女らなくして米国のオーケストラは成り立たないのが現状だ。
こういったことは米国だけではない。現在、ベルリン・フィルの指揮者キリル・ペトレンコ(1972年~)はロシア人だ。ロンドン響はイタリア系のアントニオ・パッパーノ(1959年~)、パリ管弦楽団のクラウス・マケラ(1996年~)はフィンランド出身、日本のNHK交響楽団のファビオ・ルイージ(1959年~)もイタリア人だ。各オーケストラの楽団員も多国籍である。楽団員の出自だけではない。新旧の映像を見比べれば一目瞭然なのだが、かつて男性ばかりだったのに、今では数多くの女性団員がいる。国籍も性も、まさに多様性の時代になったのだ。それでオーケストラの質が下がったのかといえば、まったく逆で、どの楽団の演奏水準も以前よりはるかに上がっている。ポストを求めて応募する人数が増えれば、それだけ優秀な人材を得やすくなるのだから当然だ。
音楽の世界だけではない。スポーツも大学や研究機関、IT産業など、あらゆる分野に通ずることだ。とりわけ米国の文化、豊かさは、移民や外国人の力、すなわち多様性に負うところが大きい。底辺が広ければ広いほど高い山を築くことができる。そんなことは砂場で遊ぶ子どもでも知っていることだ。それに気づかない者は愚か者と呼ばれよう。トランプ大統領とその取り巻き連中は、まさにそれである。わが国で「日本人ファースト」などと叫んでいる者も同類だ。「貧すれば鈍する」と言うが、逆に「鈍すれば貧する」も成り立つ。ヨソの国を心配する以前に、まずは自国のことを気にかけた方が良さそうだ。
::: C D :::
1)ミトロプーロスのシェーンベルク
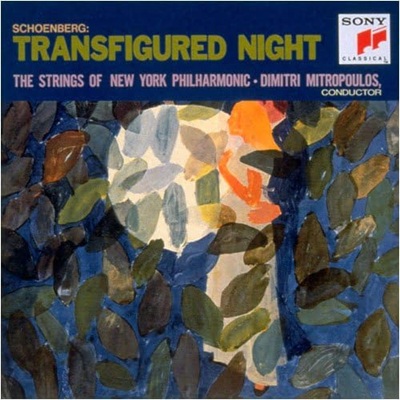
早くから新ウィーン学派の作品の演奏に挑戦していたミトロプーロスだが、リヒャルト・デーメル(1863~1920年)の同名の詩にもとづき、月下の男女の語らいを題材としたこの作品は、作曲者シェーンベルクが没して間もない七年後の録音である。官能性と情念を濃厚にはらんだ熱くて劇的な表現は、まさに後期ロマン派の最果てであり、また表現主義へと向かいつつある新しい美学への予兆でもある。その移り変わり行く時代の雰囲気を見事に表現した演奏ではなかろうか。
1.シェーンベルク:『浄夜』作品4(1943年、弦楽合奏版)
2.ヴォーン・ウィリアムズ:『タリス幻想曲』(1910年)
指揮:ディミトリ・ミトロプーロス
演奏:ニューヨーク・フィルハーモニック
録音:1958年
2)ミトロプーロスのプロコフィエフ
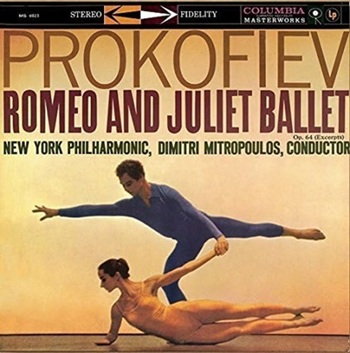
バレエ演目としての『ロメオとジュリエット』は、チャイコフスキーの三大バレエと並ぶほど人気があるのに、レコードでも演奏会の曲目としても、取り上げられるのはほんの一部だけのことが多い。全曲でなくて良いから、もう少し聴かせてほしい。そうした期待にこたえる一枚になっている。即物的な感触や無機的なモダニズムこそがセルゲイ・プロコフィエフ(1891~1953年)の特徴だが、この演奏を聴いていると、ミトロプーロスほどプロコフィエフを自家薬籠中として表現できる指揮者はいないのではなかろうかとさえ思えてくる。その独特な無造作で無骨な表現が、まさにプロコフィエフらしさを醸し出す。
プロコフィエフ:『ロメオとジュリエット』抜粋 作品64(1936年)
指揮:ディミトリ・ミトロプーロス
演奏:ニューヨーク・フィルハーモニック
録音:1957年
3)ラインスドルフのマーラー、ワーグナー
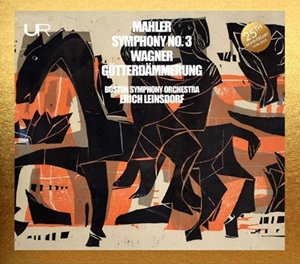
自身がユダヤの血を引くラインスドルフはグスタフ・マーラー(1860~1911年)を積極的にとりあげた指揮者だった。と同時に、反ユダヤ主義者でもあったリヒャルト・ワーグナー(1813~83年)の歌劇、楽劇をも得意にし、それはメトロポリタン歌劇場の人気演目でもあった。作曲家の出自や思想ではなく、音楽としての作品を大事にしたと言うことなのだろう。第3番は、マーラーの交響曲の中で最も長い作品である。得意としたワーグナーの作品がカップリングされているのも嬉しい。楽劇『神々の黄昏』から管弦楽の聴かせどころを抜粋したもので、ボストン響によるワーグナーなど、ちょっと聴けない曲目である。
1.マーラー:交響曲第3番ニ短調(1896年)
2.ワーグナー:楽劇『神々の黄昏』抜粋(1874年)
独唱:シャーリー・ヴァーレット(メゾ・ソプラノ:1)
合唱:ニューイングランド音楽院合唱団(1)
ボストン少年合唱団(1)
指揮:エーリヒ・ラインスドルフ
演奏:ボストン交響楽団
録音:1966年(1)、1965年ライブ(2)
4)ラインスドルフのプロコフィエフ

ラインスドルフは、前任者ミュンシュの築き上げたカラフルなサウンドを維持しつつ、入念で厳しいリハーサルによってオーケストラの合奏力の高めた結果、近代作品で聴かれる機能的な美しさとダイナミズムの共存を可能にした。このプロコフィエフ作品などは、弦楽の魅力を前面に打ち出した、まさにその成果だろう。
1.プロコフィエフ:交響曲第2番ニ短調 作品40(1925年)
2.プロコフィエフ:交響曲第6番変ホ短調 作品111(1947年)
指揮:エーリヒ・ラインスドルフ
演奏:ボストン交響楽団
録音:1969年(1)、1965年(2)
5)オーマンディのレスピーギ

オーマンディはオットリーノ・レスピーギ(1879~1936年)のローマ三部作を1958年にも録音しているが、これは15年後のもの。名手が揃った管楽器群、とりわけ明るくのびやかな金管セクションが印象的である。ゴージャスな響きではあるが、それは核になる分厚くしなやかで豊麗な弦楽セクションあってのもの。バイオリニスト上がりでバランス感覚に秀でたオーマンディらしいところである。こけおどしのような演奏が散見する中で、この曲の瑞々しさをきちんと引き出しているところがにくい。
1.レスピーギ:交響詩『ローマの松』(1924年)
2.レスピーギ:交響詩『ローマの祭』(1928年)
3.レスピーギ:交響詩『ローマの噴水』(1916年)
指揮:ユージン・オーマンディ
演奏:フィラデルフィア管弦楽団
録音:1973年(1)、1974年(2,3)
https://youtu.be/tI4WaYznZFE?si=ae7Z0OORNJyslLOL
6)オーマンディのフランク、ダンディ

ベルギー生まれのセザール・フランク(1822~90年)は、自身がオルガン奏者でもあったからだろう、オーケストラ曲にもオルガン的な響きを持ち込んでいるところが特徴だ。しかも転調や楽想の変転の妙が、まるでバッハの音楽を想起させる。フィラデルフィア管弦楽団の重厚な弦楽群が低音から高音まで積み重なるような層をなしているからに違いない。ヴァンサン・ダンディ(1851~1931年)の『フランス山人の歌による交響曲』は、交響曲と銘打っているものの、実際はピアノ協奏曲に近い。瑞々しい水の流れのようなオーケストラの上を、カザドシュのピアノがクッキリした泡粒のように浮かぶ。両者による音作りは濃厚な情熱たっぷりだが、決して過度ではなく品良く聴かせる。ピアノと管弦楽のバランスも秀逸だ。
1.フランク:交響曲ニ短調(1888年)
2.フランク:交響的変奏曲(1885年)
3.ダンディ:フランス山人の歌による交響曲
指揮:ユージン・オーマンディ
演奏:フィラデルフィア管弦楽団
ロベール・カザドシュ(ピアノ)
録音:1961年(1)、1958年(2,3)
7)ライナーのバルトーク

「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」の巧みなダイナミクス、伸縮自在なテンポ設定、それらが生み出す快いスピード感と弾力性あるメリハリ。このスリリングさは、まさにこの演奏の最高峰と言って良いであろう。シカゴ響という卓越した機能性を有するオーケストラだからこそ可能になった輝きと緊迫した表現が聴きどころの「管弦楽のための協奏曲」も、さすがライナーである。楽団員に対しては厳しかったが、同郷のベラ・バルトーク(1881~1945年)への尊敬と愛情は半端ではない。
1.バルトーク:管弦楽のための協奏曲(1943年)
2.バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽(1936年)
3.バルトーク:ハンガリーの風景(1931年)
指揮:フリッツ・ライナー
演奏:シカゴ交響楽団
録音:1955年(1)、1958年(2,3)
8)ライナーのドヴォルザーク

ドヴォルザーク(1841~1904年)の『新世界』は人気の曲だから録音も多いが、私にとってはイシュトヴァン・ケルテス(1929~73年)とウィーン・フィル、フェレンツ・フリッチャイ(1914~63年)とベルリン・フィルによるレコードと並ぶ三大名盤のひとつである。揺るぎない造形美、張り詰めた緊張感は、まさにライナーならではのもの。聴いていて圧倒されてしまう。シカゴ響の完璧といって良いアンサンブル、重厚で引き締まった音が、この曲を通俗的だなどと揶揄する者たちを蹴散らしてくれるだろう。なお、ライナー、ケルテス、フリッチャイ、みなハンガリー生まれなのは偶然の仕業だろうか。
1.ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調『新世界より』作品95(1893年)
2.バルトーク:管弦楽のための協奏曲(1943年)
指揮:フリッツ・ライナー
演奏:シカゴ交響楽団
録音:1957年
9)セルのコダーイ、プロコフィエフ

ゾルターン・コダーイ(1882~1967年)による『ハーリ・ヤーノシュ』は、ジングシュピールと呼ばれる歌をまじえた芝居。オペレッタに似た、オペラとミュージカルの中間的な大衆演劇とでも言えば良いだろうか。それを再編したのがこの組曲版である。一方の『キージェ中尉』は映画のための音楽で、映画公開時に演奏会用の組曲として、オーケストレーションその他にかなり手を入れた上で作られた。前者は主人公の冒険と出世についてのホラを語る芝居であり、後者は実在しないキージェなる人物を主人公に据えた映画という、どちらも笑える娯楽作品なのだが、それを純音楽として昇華し、格調高いものにしているところなど、さすがにセルである。コダーイが収拾した民族音楽やストーリーが単に面白おかしく描かれるのではなく、完璧な演奏から自然と立ちのぼるユーモアと皮肉にとって、両曲の最良の演奏になっている。
1.コダーイ:組曲『ハーリ・ヤーノシュ』
2.プロコフィエフ:組曲『キージェ中尉』
指揮:ジョージ・セル
演奏:クリーブランド管弦楽団
録音:1969年
10)セルのバルトーク、ヤナーチェク

1918年、第一次大戦でオーストリアが敗れ、その圧制下に苦しめられていたブルノの町は息を吹き返した。ここに住んでいたレオシュ・ヤナーチェク(1854~1928年)は嬉しくてたまらなかったのだろう、曲の冒頭のファンファーレにそれが現れているようだ。オーストリア支配下のハンガリーに生まれ、新天地アメリカという活躍の場を得たセルには、政治や社会的な苦悩からの解放は、まさに我がことだったのだろう。そのコンパッションにあふれた演奏になっている。同郷のバルトークについては、これもまた同郷のライナーの演奏とくらべてほしい。同じハンガリー出身でも、オーケストラを厳しく鍛え上げる姿勢が似ていても、そこから導き出される音楽はこれほどにまで違うところが、当たり前ながら面白い。
1.バルトーク:管弦楽のための協奏曲
2.ヤナーチェク:シンフォニエッタ
指揮:ジョージ・セル
演奏:クリーブランド管弦楽団
録音:1965年
(しみずたけと) 2025.11.18
9jブログTOPへ
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ