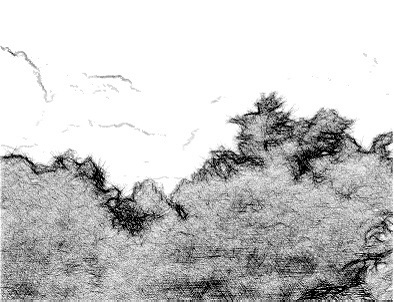ひとりひとりの彼ら
うんざりする平野の蒸し暑さはここにはないだろう
だが、見上げた木立の葉っぱの向こうには
太陽の熱が見える
剥き出しのコンクリートの壁に掛けられた絵
とある一枚の正面に立つ
聞こえないかと耳をすます
横に歩を進める
一枚一枚の絵、ひとりひとりが見える
絵を描きつづけたかった
わたしが後悔したところで
彼らは戻ってこない
心の底の思い
15年くらい前に観てきました。 ひとことで言って、全体にとても悲しく、重苦しい印象でした。 どの作品も、デッサンは青年らしい若々しさを感じるのに、 色調が暗いのです。
おそらく、これらを描いた青年たちの心の底には、反戦の思いが強くあったに違いない、自分が生きて帰ることはあり得ないと固く信じていて、たとえ表向き、お国のために喜んで戦地に向かうと口にしても、最後の絵には、心の底の思いが色彩に現れてしまったのだろうと想像し、息がつけなかったことを思い出します。
シベリヤ抑留時を描いた香月泰男画伯の、濃い茶系統の色調と思い合わせ、彼らの未経験の痛ましさを一層感じます。
2020年6月記
毎年毎年、何の変わりもなく同じ事を繰り返すことができるということ
自然に惹かれて、長池里山クラブで20年以上活動してきた青木といいます。昨年、長野に転居しました。生まれは京都で、大学を出るまで過ごしました。
小学校入学の年に開戦、5年生の時に終戦。五条通りを拡げるための強制疎開は異様な風景でした。体操の授業では全員にピンタ(ほっぺたを叩かれる)のが常で、これも道理がありません。白米が手に入りにくくなり、大根を入れて増量。もちろん美味しくない。給食に出たパンには藁が入っていました。校庭の半分に、サツマイモや枝豆を植えました。
B29の大編隊が1万メートル上空にやって来るようになり、夜は屋根に上ると大阪方向の空が炎で赤く染まっていることが続きました。空襲警報が鳴ると和室の床下に作った小さな防空壕に飛び込みました。B29の爆音とサイレンの音は、今でも耳に記憶が残っています。
近くから飛び立った赤トンボ(日本の木製練習機)は、まるでオモチャのようでした。家の中に居た時、突然アメリカの戦闘機がすぐ近くに迫って来て、バリバリバリと機関銃の音、近くにいた母が私の上に布団を被せ、被さるようにのっかかりました。西山のトンネルの近くに(工場でもあったのか)爆弾が落ちたという話も聞きました。京都は爆撃に会わなかったと言うのはウソです。気に入らない情報は禁止されていたのです。子供ながら、何か暗い圧迫感や恐怖の ようなものを感じていました。
今の時代も何となく、子供の時に感じたものと似てきて恐ろしく思われます。私にとって戦争は細かな体験、記憶でしかないのですか、周りを見ると政治家をはじめ多くの人たちが、戦後の生まれであることに驚きと不安を感じています。
私のいまの家から40分~50分で行ける所に「無言館」があります。知人、友人が来てくれる時には別所の寺巡りコースに、必ず「無言館」を入れています。もう10回を超えていると思います。展示されている作品や手紙の中に、私の義兄と美校で同期だった友人も含まれていて、より身近に感じています。義兄は100歳で去年亡くなりましたが、戦争がなかったら、どんな人生を送っていたことでしょう。
あとで建設された二号館には京都の美校の先輩の絵が飾られています。館を出る時に私がいつも思うのは、俺は今何をしているのだろう、いい人生を送っているか、これでいいのか、と言う現在の自身の不甲斐なさです。そう感じてしまうのです。残念ながら1日経つとそれも無くなってしまうのですが。
長池公園では、コナラを伐採し、玉切り、薪割り、炭作りを経験しました。冬の餅つき、門松作り、どんど焼きもやりました。春には田植え、秋には稲刈り。それが、長野に転居してからも、米作りこそしないけれど、似たようなことを続けている自分がいます。こちらでは、まだ一年目ですが多分、身体が動ける間は続けるでしょう。そして思うのです。毎年毎年、何の変わりもなく同じ事を繰り返すということが、いかに大切で大事なものなんだと。自然の中で森の空気をいっぱい吸って、植物の成長に感動し、畑で収穫したものを美味しくいただくということ。これは実はずっと昔から人間がやって来た事なのです。仲間が増え交流ができる、そうしたことが幸せと言うものなのかも知れません。人間が人間らしく生きることこそが、とても大事だと、この歳になって改めて 感じるのです。
2020年6月記




無言館、再訪
入口の扉を開けて入ると、そこは十字架の形をしたフロア。まるで教会のような空間である。すぐ右側の壁に、その絵はあった。日高安典作、「裸婦」。
この絵を見ようと、お盆あけの八月の一日(ひとひ)、無言館を訪ねた。戦没画学生の遺作を所蔵・展示する、長野県にある美術館。前に来たとき、まだ第二展示館(2008年開館)はなかった。十年以上も足が遠のいていたのか…。
「生きて帰ってきたら、絵の続きを描くから」と言い残して出征した日高は、1945年4月19日、フィリピンのルソン島で戦死した。1918年生まれだから、享年27才。左側にある絵は「ホロンバイル高原」と題する内蒙古の風景。ああ、関東軍に配属されたのか。
太平洋方面の戦況悪化により、大陸の関東軍も南方戦線に投入された。1944年10月、日高はフィリピンへ転戦。父から聞いたこと。「ある晩、南に送られる関東軍が八列縦隊で北京を後にした。それが最後の姿だった」と。その中に、彼もいたのだろうか。
10月20日から25日のレイテ沖海戦で日本海軍は壊滅し、戦局は既に決していたはず。そんなところへ、なぜ兵力を投入したのか。制海権を手にした米軍は、激しい艦砲射撃で海岸陣地を破壊し、日本軍を山岳地帯へと追いやった。そこへ、制空権のない日本軍には手の届かぬ空からの容赦ない爆撃。日高は米第一軍団との戦闘の中で戦死したのだろう。その一週間後の4月26日、拠点のバギオが陥落。戦争は、あと四ヶ月で終わったというのに…。
無言館が編集・刊行する『新版 戦没画学生人名録』をひもとくと、終戦近くのフィリピンで亡くなっている者がかなり多いことがわかる。ほかに、広島で被爆死した者、特攻隊員として出撃していった者、旧満州の牡丹江や雲南省のビルマ(現ミャンマー)国境付近など、自分が訪れたことのある戦地の名前が見える。そして沖縄では8月15日以降の戦死者も…。
アジア太平洋戦争は、日本による侵略戦争であった。大きな被害を蒙ったが、加害の側面もまた大きい。画学生とはいえ、彼らも兵士。その手にかかった敵兵もいたであろう。
殺(や)らなければ殺(や)られる、そうした狂気の世界。しかし、生まれながらの鬼畜がいようはずがない。赤ん坊を見ればわかることだ。敵味方関係なく、何が彼らを鬼に仕立てあげたのか。その仕組みに目を向けないかぎり、同じことがくりかえされることになる。
戦争によって断ち切られてしまった才能と人生。中国やアメリカなど、戦った相手側、そして巻き込まれた現地住民の中にも、同じような境遇の者がいたであろう。彼らの無念を晴らすには、同じ轍を踏まない、それ以外に何があるだろうか。
8月15日放送のNHK『日曜美術館』を見た。窪島誠一郎館長が、日高安典の「裸婦」にまつわるエピソードを語っている。無言館が開館(1997年)して二年後の夏、この絵のモデルとなった女性が来館。日高への思いや制作の様子を、半世紀の時を経て、そっと感想文ノートにしたためていった。来館を告げることもなく…。
その文言から伝わってくる思い、苦悩とか悲哀などという陳腐な言葉では言い表せない、もっとふさわしい表現を、私は見つけることができない。戦争は、生き残った者さえ、終わりのない悲しみの檻に捕らえて放さない。感想文ノートは「無言館日誌」としてまとめられているようだから、機会があれば、自分の目で全文を読んでみたいものだ。戦争の恐怖と戦争への怒りを忘れないために、そして戦争をしたがる者たちと闘うために。
日高安典は鹿児島県種子島の出身。そういえば、親しい友人に、やはり鹿児島出身がいた。種子島か、屋久島だったか。同じ日高の姓。縁あるものではないかもしれないが、いちど訪ねてみようと思う。
(しみずたけと) 2021年9月記
日高安典「裸婦」 1) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collection_of_Mugonkan...
同「ホロンバイル高原」 2) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collection_of_Mugonkan...