モーツァルトに始まる一連のレクイエム紹介のきっかけは、ウクライナ戦争に心を痛めたからだった。しかし、ベンジャミン・ブリテン(1913~1976年)の『戦争レクイエム』をとりあげたのは、ウクライナ戦争が始まる半年以上も前になる。もとより鈍感な人間であるから、予感の類であるはずがない。歴史に残る大作曲家たちによるいくつかのレクイエムをまとめて聴きなおす機会にはなったが、心は少しも晴れないままだ。
無信仰者の私だが、これも何かの啓示かもしれない、『戦争レクイエム』を改めて聴きなおすことにした。
歌詞に用いられているのは、オーソドックスなラテン語の典礼文とウィルフレッド・オーウェン(1893~1918年)による英語の詩だが、両者の比重はほぼ同じ。その接続は実に巧みにされているという。生まれつき病弱だったオーウェンが第一次大戦に従軍し、敵弾に倒れたのは休戦一週間前だった。総譜の冒頭にあるのは彼の言葉である。
「私の主題は戦争であり、また戦争の悲哀である。そして詩は悲しみの中にある。詩人のなし得るすべてのことは、警告することなのだ」
戦争レクイエム
曲は六つの楽章で構成されている。
第1楽章 永遠の安息を
・主よ、永遠の安息を彼らに与え給え
・家畜のように死んでゆく兵士たちに
第2楽章 怒りの日
・その日こそ怒りの日である
・夕べの大気を悲しげに
・そのとき、この世を裁く
・戦場で、ぼくたちはごく親しげに
・慈悲深いイエスよ
・汝の長く黒い腕が
・怒りの日
・罪ある人が裁かれるために
・彼を動かせ
第3楽章 奉献文
・栄光の王、主イエス・キリストよ
・かくて、アブラハムは立ちあがり
第4楽章 聖なるかな
・聖なるかな、聖なるかな
・東方から一筋のいなずまが
第5楽章 神の小羊
・かりそめにも爆撃された
第6楽章 我を解き放ちたまえ
・主よ、かの恐ろしき日に
・ぼくは戦闘から脱出して
・さあ、もう眠ろうよ
::: C D :::
前回は作曲者自身の指揮による1963年の演奏だったが、今回はなるべく新しい録音のものを選んだ。小澤征爾(1935年~)とサイトウ・キネン・オーケストラによるライブである。満洲に生まれた小澤は、日本で教育を受け、欧州で認められ、米国で成功し、西洋音楽の世界で確固たる地位を得た人物である。西洋と東洋の接するところに生き、両者の優れたところとそうでないところを肌で感じとってきた人間だけが持つ、俯瞰的な視点。私はそれを感ぜずにはいられない。
小澤征爾のつくり出す音楽は、時に淡泊、時に熱く、そして純音楽的。彼を含め、音楽家が政治について語ることはほとんどないと思われがちだが、彼が政治に無関心な人間だということにはならない。戦争末期、満洲から引き揚げ、一家で立川に暮らしていた彼は、米軍のP51戦闘機が、軍事的必要性からではない、子どもや一般市民に対する無差別な機銃掃射を目撃し、こう語っている。
「恐らくふざけてやっていた気がするな。桑畑なんて撃つ必要がないんだから」
同級生の自宅は直撃弾によって一家三人が即死したと言う。これは朝日新聞(2013年9月19日)に載ったインタビュー記事である。記事の題名は「日中関係《大事なのは一人ひとり》」。尖閣列島の領有をめぐり、日中関係が冷え込んでいく時期だった。
「俺なんか全然冷え込んでないよ。冷え込んでいるのは、日中政府間の関係。大事なのは一人ひとりの関係で、ぼくは、中国にいる友人たちを信じている(中略)人間生きていくときにね、俺の政府と、お前の政府との仲が冷え込んでいるからって俺には何の関係もないよ。ぼくはまったく心配していない。中国にいる僕の仲間だって心配してないと思う(中略)政府がどう言ったからだとか、新聞が書いているから、とかじゃなくて。大事なのは一人ひとり。政府よりも、政府じゃない普通のひとがどう考えるかが一番大事。僕はそう思う」
1979年、手兵のボストン交響楽団を率いて中国公演をおこない、中国のオーケストラとも合同演奏会を実現した彼の言葉には重みがある。それで思い出したのは、別のTVインタビューでのこと。聴き手がいろいろな単語をあげ、それに答えるという趣向だった。その中の一問一答。
Q.航空母艦
A.無駄なもの
小澤征爾の音楽から政治性が排除され、純粋な音楽としての昇華こそが柱になっているのだとしたら、それは彼が政治に対して無関心なのではなく、政治の貧困、歪んだ政治の無力さゆえなのだろう。いつの時代も、音楽は政治に利用されてきた。いや、政治と結びつくことによって生きながらえてきたという側面も否定できない。
権力が音楽を利用してきたと同様、それに抗する民衆もまた、音楽によって団結してきたのもまた事実である。なぜなら、音楽というものは、人々に生きる勇気を与えるためのものであるから。また、そうあるべきであるから。音楽にかぎらず、絵画、写真、映画など芸術全般、文学などにも言えることである。
米国の国際政治学者サミュエル・ハンティントン(1927~2008年)は、現代の国家間の対立を「文明の衝突」と呼んだ。彼の言う文明が、何によって構成されるものなのかが今ひとつわからないのだが、おそらく文化は含まれていないのだろう。言語や宗教が違うからと言って、人は必ずしも対立したり争ったりするわけではない。利権や富の配分、その不均衡や不公正さこそが主たる原因になっている。それを容認し、むしろ推進しているのが政治である。いや、政治それ自体がそのことを目的としているからにほかならない。
「大事なのは一人ひとり」は、彼が自我を確立した個人、市民社会に生きる人間であることを表している。それが中国大陸に生まれたことによるものなのか、欧米社会に長く身を置いたせいなのかはわからないが、多くの日本人とは異なっている特質であろう。私が「小澤征爾は日本人ではない」と思うのは、民主主義の理解度の相違、まさにこの点にある。
その小澤征爾による、長野県松本文化会館での『戦争レクイエム』である。こうした大曲、大編成のオーケストラを操る巧みさは昔からだし、世界で活躍する演奏者が結集したサイトウ・キネン・オーケストラの機動性は折り紙付き、独唱も合唱も文句なしの出来映えなのだが、このライブはそれだけにとどまらない。咽頭ガン手術のあと、まさに命を削るかのような鬼気迫る彼のバトンは、ステージ上すべての演奏家の魂の叫びを引き出し、その温かさが聴衆の心にしみ入ってくる。
翌年、彼の『戦争レクイエム』は、ニューヨークのカーネギー・ホールで再び演奏された。バリトンがマティアス・ゲルネに変わったほかは、ほぼ同じ顔ぶれ。音の良さで定評のある会場だが、松本文化会館も負けていない。以前、スタジオ録音とライブの違いを、ラファエル・クーベリックの『マーラー交響曲第5番』で聴きくらべてもらったことがあるが、今回の聴きくらべはホールと聴衆ということになろうか。オザワ渾身の『戦争レクイエム』を、とにかく聴いてほしい。
1)2009年 松本文化会館
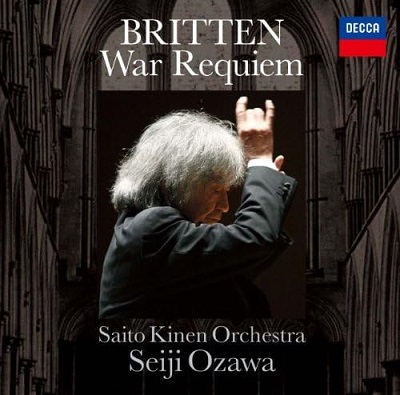
独唱:クリスティン・ゴーキー(ソプラノ)
アンソニー・ディーン・グリフィー(テノール)
ジェイムズ・ウェストマン(バリトン)
合唱:SKF松本合唱団、東京オペラシンガーズ
栗友会合唱団、SKF松本児童合唱団
指揮:小澤征爾
演奏:サイトウ・キネン・オーケストラ
2)2010年 ニューヨーク カーネギー・ホール
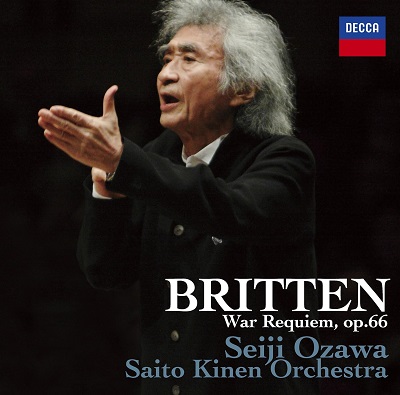
独唱:クリスティン・ゴーキー(ソプラノ)
アンソニー・ディーン・グリフィー(テノール)
マティアス・ゲルネ(バリトン)
合唱:SKF松本合唱団、東京オペラシンガーズ
栗友会合唱団、SKF松本児童合唱団
指揮:小澤征爾
演奏:サイトウ・キネン・オーケストラ
(しみずたけと) 2023.10.5
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ