モデスト・ムソルグスキー
ピアノ組曲『展覧会の絵』
ロシアによる侵攻で、ウクライナの首都キエフの名前がクローズアップされた。おそらくチェルノブイリ原発事故以来であろう。メディアをはじめ、現在はウクライナ語の発音に近いキーウと呼ばれている。ウクライナへの連帯の意思表示であろう、ベルリン・フィルのヴァルトビューネ野外コンサートなど、この夏は『展覧会の絵』がとりあげられることが多かったように思う。
『展覧会の絵』は、歌曲集『死の歌と踊り』で紹介したモデスト・ムソルグスキー(1839~81年)による組曲で、その終曲が「キエフの大門」である。遅まきながら、ここでもウクライナへの連帯を表明したい。
『展覧会の絵』は、1873年に動脈瘤のため39才の若さで夭逝した友人、画家ヴィクトル・ハルトマン(1834~73年)の遺作展を訪れたムソルグスキーが、そこで見た絵画の印象を音楽にしたものであるという。ピアノ組曲として1874年につくられたものの、生前に演奏されることはなく、楽譜が出版されたのも1886年になってからであった。
この曲が世界的に知られるようになったのは、1922年にモーリス・ラヴェル(1875~1937年)が管弦楽曲に編曲し、同年、セルゲイ・クーセヴィツキー(1874~1951年)による初演が好評を博したからである。ロシア的な土の香りより、フランス的な明るい色彩感と暖かみのある音色に重きが置かれ、華麗なものへと変貌を遂げていることがわかる。
ラヴェル以外の編曲も多数あり、少なくとも10以上はあるだろう。しかし、今日演奏されるのは、もっぱらラヴェル版であり、録音で聴けるものを含めても、他はあまり聴く機会がない。たとえば、ヴァイオリンで始まる冒頭がロシア的な重さと渋みを感じさせるレオポルド・ストコフスキー(1882~1977年)による編曲は、録音技術が進歩し、機動性に優れた現代のオーケストラを考えると、音響的にもなかなか魅力的に思えるのだが…。(お聴きになりたい方はリクエストして下さい。)
ピアノ版の方は、ムソルグスキーの遺稿を整理したニコライ・リムスキー=コルサコフ(1844~1908年)による改訂版が長らく使われてきた。しかし、スヴャトスラフ・リヒテル(1915~97年)が、ブルガリアのソフィアで開かれたリサイタルで原典版を演奏し、そのライブ録音がリリースされると、その衝撃は大きく、これを機に原典版による演奏が主流となった。
あまりにも有名な曲なので、あとは全曲を構成する個々の表題を紹介するだけにとどめたい。
プロムナード
こびと(グノーム)
プロムナード
古城
プロムナード
チュイルリーの庭(遊びの後の子供たちの口げんか)
牛車(ブィドロ)
プロムナード
卵の殻をつけた雛の踊り
サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ
[プロムナード]
リモージュの市場
カタコンブ
死せる言葉による死者への呼びかけ
鶏の足の上に建つ小屋(バーバ・ヤガー)
キエフの大門
ラヴェル編曲版において[ ]の曲は省かれている。
::: C D :::
まずは原曲のピアノ版を聴いてみてほしい。リヒテルのソフィアでのライブ盤と思ったのだが、手元に見当たらないので、ウラディーミル・アシュケナージ(1937年~)に登場願おう。①はアシュケナージの二度目の録音。1967年の一回目から大きく変わっていないのは、当時すでに演奏スタイルを確立していたからだろう。洗練度はさらに増している。近年は指揮者としても活躍しているが、マウリツィオ・ポリーニ(1942年~)、マルタ・アルヘリッチ(1941年~)と並ぶ世界最高のピアニストの一人であるのは間違いない。
当盤のもうひとつの特徴は、カップリングされているのが、アシュケナージ自身の編曲による管弦楽版であることだ。他の指揮者では聴くことができないという意味でも貴重だろう。ラヴェル版と、どこがどう違うのか、この曲に対するアシュケナージのこだわりなど、耳をこらして聴いてみてほしい。
イタリア人のカルロ・マリア・ジュリーニ(1914~2005年)は、病気がちだったこともあり、有名オーケストラの音楽監督や首席指揮者に就いた期間は決して長くなかった。しかし、つくり出す音楽は、まさに巨匠のそれだったように思う。戦争中、ファシストの手先になることを嫌い、軍から脱走、戦争が終わるまで隠れ住んだという。彼の良心、人間性を表すエピソードではなかろうか。
②で冒頭のトランペットを吹くのは名手アドルフ・ハーセス。彼をはじめ、ホルンのデール・クレベンジャーらによる強力な金管セクションを前面に出した豪奢な音響と高い機動力が自慢のシカゴ響。しかし、ジュリーニの指揮は、それらに頼ることなく、遅めのテンポで渋く重い響きを紡ぎながらも、繊細かつ伸びやかに歌わせる。ムソルグスキーのロシア的な冷たい土臭さと、ラヴェルの暖かく華やかな管弦楽効果が織り合わさった、スケールの大きな演奏を堪能できる最高の一枚だろう。
③はクラウディオ・アバド(1933~2014年)がロンドン交響楽団の首席指揮者に就任したばかり、46歳の時のものである。彼のムソルグスキーの作品へのこだわりは、『ボリス・ゴドゥノフ』と『ホヴァーンシチナ』の二つの歌劇を録音するほどであった。
『展覧会の絵』は、1993年にベルリン・フィルと再録しており、そちらは完成度と安定性では上回るものの、若さによる気迫のこもったロンドン響との演奏の方がはるかに魅力的だ。ジュリーニの演奏が暖色的な絵画だとしたら、こちらは寒色系の色合いを強調したクールな画法とでも表現したら良いだろうか。聴きくらべてみるのも楽しい。
セルジュ・チェリビダッケ(1912~96年)は、大好きか大嫌いかというように、好みがハッキリ分かれる指揮者であった。④の録音も、クセが強いと言うか、個性的と表現すべきか、特異な存在である。全曲の演奏時間が、ジュリーニと比較して約10分、アバドより11分も長い。これほどゆっくりしたテンポで演奏する指揮者は他にいるまい。それでいてアンサンブルは少しも乱れることなく、積み重ねられた豊潤な響きを、ゆるゆると、しかし緊張感をたもちながら進行していく。ミュンヘン・フィルの腕前、恐るべし…。
聴衆は展覧会場に足を踏み入れた途端、時が過ぎゆくのを忘れて絵を鑑賞し、いつしか鐘の鳴り響くキエフの大門をくぐろうとしている。割れんばかりの拍手の中、ふと自分がミュンヘンのフィルハーモニー・ガスタイクにいるような感覚に…。喝采が静まり、ようやく我にかえる。メインストリームではないかもしれないが、大きな感動を与えてくれる一枚である。
収録曲
1)アシュケナージ盤
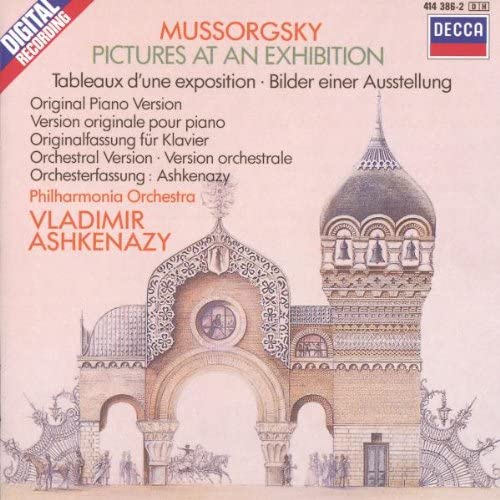
収録曲
1.ピアノ独奏版
2.アシュケナージによる管弦楽編曲版
独奏:ウラディーミル・アシュケナージ(ピアノ)
指揮:ウラディーミル・アシュケナージ
演奏:フィルハーモニア管弦楽団
録音:1982年
2)ジュリーニ盤
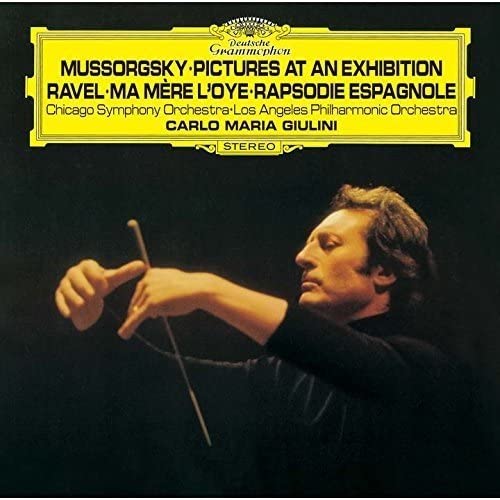
収録曲
1.ムソルグスキー:組曲『展覧会の絵』
2.ラヴェル:マ・メール・ロワ 作品60(1910年)
3.スペイン狂詩曲 作品54(1907年)
指揮: カルロ・マリア・ジュリーニ
演奏: シカゴ交響楽団(1)
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団(2-3)
録音: 1976年(1)、1979年(2-3)
3)アバド盤
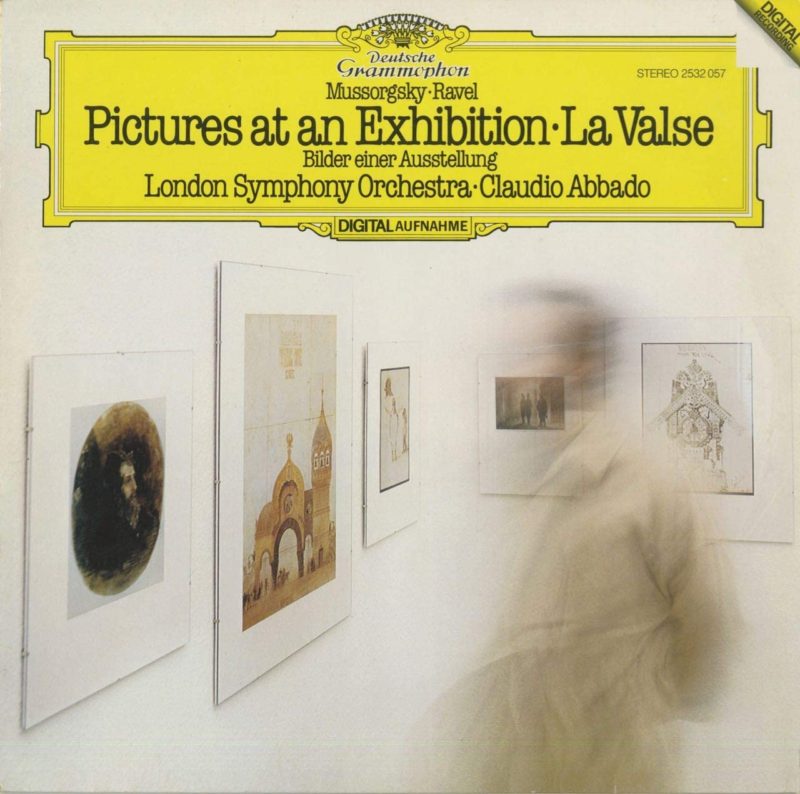
収録曲
1.ムソルグスキー:組曲『展覧会の絵』
2.ラヴェル:ラ・ヴァルス 作品72(1920年)
指揮: クラウディオ・アバド
演奏: ロンドン交響楽団
録音: 1991年
4)チェリビダッケ盤
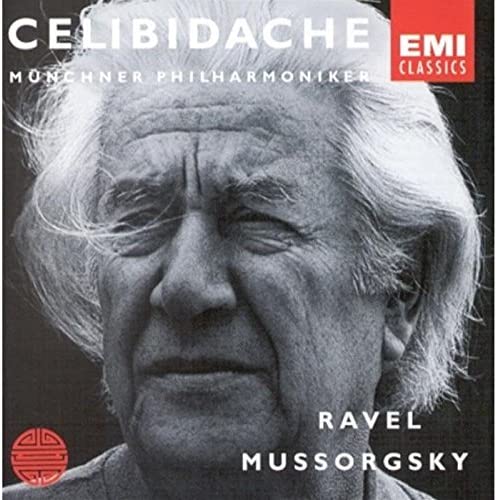
収録曲
1.ムソルグスキー:組曲『展覧会の絵』
2.ラヴェル:ボレロ 作品81(1928年)
指揮: セルジウ・チェリビダッケ
演奏: ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
録音: 1993年(1)、1994年(2) ライブ
ラヴェル編曲による三つの盤の演奏時間を比較すると・・・
| ジュリーニ | アバド | チェリビダッケ | |
| プロムナード | 1:50 | 1:47 | 2:33 |
| こびと | 2:40 | 2:24 | 3:30 |
| プロムナード | 1:07 | 1:03 | 1:29 |
| 古城 | 4:31 | 4:22 | 5:10 |
| プロムナード | 0:37 | 0:33 | 0:45 |
| チュイルリーの庭 | 1:16 | 1:05 | 1:17 |
| 牛車 | 2:39 | 3:16 | 3:45 |
| プロムナード | 0:48 | 0:45 | 1:09 |
| 卵の殻をつけた雛の踊り | 1:21 | 1:13 | 1:22 |
| サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ | 2:24 | 2:07 | 3:01 |
| リモージュの市場 | 1:30 | 1:15 | 1:37 |
| カタコンブ | 2:06 | 3:58 | 2:33 |
| 死せる言葉による死者への呼びかけ | 2:09 | ―― | 2:56 |
| 鶏の足の上に建つ小屋 | 3:54 | 3:30 | 4:22 |
| キエフの大門 | 5:44 | 5:46 | 6:52 |
(しみずたけと) 2022.9.9
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ
先日の日曜にアマデウス・ソサイエティー管弦楽団がすみだトリフォニーで、11月にはズーラシアン管弦楽団がオペラシティで展覧会の絵(を含む)を演奏する(した)と言うことらしいです。直近でふたつもあり、ほんとうにポピュラーな曲なんだなあと実感します。ネット検索してみる人もなかなかにありそうです。
8月にはNHKラジオで放送されたらしいし。
ムソルグスキーが存命中に演奏されなかったとは、お気の毒としか言いようがない。
Ak.