ベドルジハ・スメタナ
ヨーロッパにおける市民のための音楽、さらには東欧のビロード革命の発火点にまつわる逸話として、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団とクルト・マズアについて触れたことがある。あのライプツィヒの「月曜デモ」は、音楽家マズアらの尽力によって流血の事態を避けることができたが、またたく間に中欧・東欧に伝播した民主化運動は、それを抑え込もうとする国家権力との対立を巻き起こす。チェコでも、音楽は武器を持たない一般市民を勇気づける役割を担った。ここで紹介するスメタナの『わが祖国』も、そのひとつである。
『わが祖国』は、ボヘミア(現在のチェコ)のベドルジハ・スメタナ(1824~84年)が、1874年から1879年にかけて個別に作曲した6つの交響詩からなる作品である。民族主義につながる国民楽派の先駆者であった彼は、オーストリア=ハンガリー二重帝国の支配に苦しむ祖国の解放と独立への願望を胸に、この曲を通して故郷の歴史や伝説、景観を描いた。いつの時代も、民衆に勇気を与え、そしてその民衆から愛されてきた、チェコの人々にとって特別の存在だと言えよう。
第1曲:高い城
チェコの首都プラハにある、今は廃墟となったヴィシェフラド城のことで、ボヘミア王国時代は国王の居城だった。この国の著名人が眠る民族墓地があり、スメタナの墓所もここである。ハープによる、まるで竪琴を手にした吟遊詩人が、この国の栄枯盛衰を語るかのような冒頭の主題が、6曲全体の流れを導いてゆく。
第2曲:モルダウ
モルダウはドイツ語名で、この地方ではヴルタヴァと呼ばれる川の名前。下流はエルベ川となる。モルダヴィア地方に伝わるこのメロディは、イスラエル国歌『ハティクヴァ―希望』のもとにもなっている。単独で演奏されることもあり、6曲の中では最も知名度が高い。学校の音楽の授業で聴いたという人もいるだろう。
第3曲:シャールカ
8世紀頃のこと。女性たちは、自分らを見下し、支配する男たちに怒り、武器を手に立ち上がった。女と男の間に戦が起きたのである。シャールカは、何人もの女性を殺めてきた強敵ツチラトがプラハ城に向かうところを、はかりごとを巡らせて打ち倒す。この曲は、「女たちの戦い」と呼ばれる中世の伝説を下敷きにしたもの。プラハの北西にある渓谷美がすばらしいディヴォカー・シャールカという自然保護区は、彼女の名にちなむものである。
第4曲:ボヘミアの森と草原から
鬱蒼とした森を背景に、明るい夏の太陽と収穫を喜ぶ農民が歌い、踊り、神に祈りを捧げ、民族舞踊ポルカへと続く。
第5曲:ターボル
教会の堕落を批判したために焚刑に処せられたヤン・フス(1369~1415年)。その宗教改革運動を受け継いだ者たちは、18年にわたるフス戦争を戦った。その拠点のひとつが、ボヘミア南部の町ターボルである。戦いに敗れはしたものの、チェコの人々は民族的結束力を強めることになった。
第6曲:ブラニーク
ブラニークは、フス派戦士たちが眠ると言われるボヘミア中部の山。第5曲の「ターボル」から続くものとなっていることは、ともにフス派の聖歌『汝ら神の戦士』が使われていることからもわかる。最後は「高い城」の冒頭主題が、ここでは未来の希望として勇壮に再現され、クライマックスとなる。
< CD >
有名なだけあって、『わが祖国』の録音は多い。LPレコードの時代の話ではあるが、収録時間の関係で、第2曲の「モルダウ」は、ドヴォルザークの交響曲第9番『新世界より』とカップリングされることが多かった。全曲録音は、やはりチェコの指揮者の十八番である。
同じ指揮者による複数回の録音も珍しくないので、生年順に並べてみると、ヴァーツラフ・ターリヒ、ヴァーツラフ・スメターチェク、カレル・アンチェル、ラファエル・クーベリック、ヴァーツラフ・ノイマン、イルジー・ビエロフラーヴェクといったところが思いつく。どの演奏が良いとか良くないとかは言うまい。各自がお好きなものを選んで聴いてほしい。
ここでは、ビロード革命と呼ばれる、私たちが目撃し、同じ時代を生きるチェコの人々と、民主主義や人間の尊厳の大切さを分かち合うという意味で、二つの演奏を紹介しておこうと思う。
①ノイマン盤
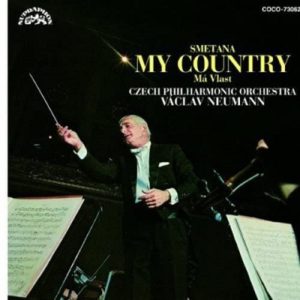
指揮:ヴァーツラフ・ノイマン
演奏:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1975年
1989年のビロード革命で、ノイマンは一貫して民主派側につき、11月17~20日の連日に渡ってスメタナホールでこの曲を演奏し、学生を中心とした活動家たちを応援した。朴訥とした演奏の中に漂う色彩感と情感は、国家という体制ではなく、やはり土地に根ざした祖国愛から来るものなのだろう。この録音は、1968年にチェコ・フィル首席指揮者に就任して約7年、オーケストラとの緊密化された関係をうかがわせるダイナミックな曲作りになっている。
②クーベリック盤
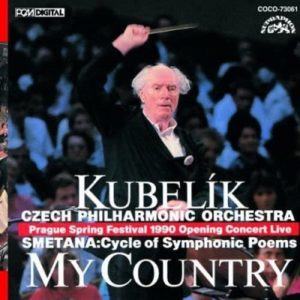
1941年にチェコ・フィルの首席指揮者に就任したクーベリックは、46年5月12日、この年に始まったプラハの春音楽祭で『わが祖国』を振った。しかし、ソ連の影響力が強まる中、48年2月に起きたチェコスロバキア政変に反対し、エディンバラ音楽祭に向かったまま西側に亡命。86年には指揮活動から引退してしまう。89年の民主化革命を契機に、ハヴェル大統領の強い要請で亡命先のイギリスから帰国し、翌90年の「プラハの春」音楽祭でチェコ・フィルを指揮し、『わが祖国』の歴史的演奏で復活した。これはその時の記録である。
指揮:ラファエル・クーベリック
演奏:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1990年(ライブ)
(しみずたけと)
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ