数多あるレクイエムも、元をたどれば中世のグレゴリオ聖歌に行き着く。前に紹介したモーリス・デュリュフレ(1902~86年)のレクイエムは、グレゴリオ聖歌の現代的解釈とでも言えば良いだろうか、グレゴリオ聖歌が20世紀に生まれたのなら、このような響きを伴うのかもしれない。
それでは、もっと中世に近い時代、ルーツであるグレゴリオ聖歌により近しい音楽はどうなのであろう。ここにとりあげたフランチェスコ・ドゥランテ(1684~1755年)の『レクイエム ト短調』なら、グレゴリオ聖歌と古典派のモーツァルトの『レクイエム』の橋渡しをしてくれそうだ。
ドゥランテはイタリアのナポリ生まれ。音楽の父と呼ばれるヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685~1750年)と同じ時代を生き、宗教曲や器楽曲、イタリア古典歌曲を残している。聖オノフリオやポーヴェリ・ディ・ジェス・クリスト、聖マリア・ディ・ロレートなど、いくつもの音楽院で教育活動に力を注いだ人で、たくさんのオペラ作曲家を輩出した。当時の音楽学校は、教会や修道院に付随しており、音楽学校を表すミュージック・コンサーヴァトリー(conservatory)は、それらが孤児や女性、病人、老人を保護する(conserve)場であったことに由来している。弟子たちに音楽を教えながらも、この人の作品は神への捧げものだったことがうかがえる。
Introitus:
1. Requiem aeternam
2. Kyrie
Gradualis et tractus:
3. Requiem aeternam – In memoria aeterna
4. Fuga in C Minor
Sequentia:
5. Dies Irae, dies illa
6. Recordare Jesu pie
7. Ingemisco tamquam reus
8. Confutatis maledictis
9. Lacrymosa dies illa
Offertorium:
10. Domine Jesu Christe
11. Hostias
Sanctus:
12. Sanctus
13. Benedictus
14. Toccata (Anonymous, Naples, XVII sec.)
15. Agnus dei
Communio:
16. Lux aeterna
Exitus:
17. Libera me domine
::: CD :::
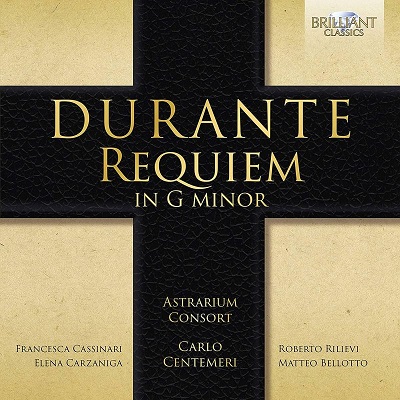
レクイエム ト短調(1746年)
耳にすることが決して多いとは言えないドゥランテの『レクイエム』だが、英国の大学聖歌隊による合唱と演奏がそれなりに見つかる。イタリアの教会、イタリアの音楽院と深い関わりのあったイタリア人のドゥランテ。その作品ということで、ここではイタリアの演奏家によるものを選んでみた。当時、イタリアという国家はまだ現れていなかったのだけれど、そこは目をつぶってもらうとして…。
独唱: フランチェスカ・カッシナーリ(ソプラノ)
エレーナ・カルツァニーガ(コントラルト)
ロベルト・リリエーヴィ(テノール)
マッテオ・ベッロット(バス)
演奏: アストラリウム・コンソート
カルロ・チェンテメーリ(オルガン、指揮)
録音: 2018年
(しみずたけと) 2023.4.14
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ