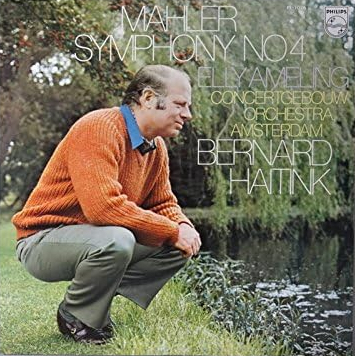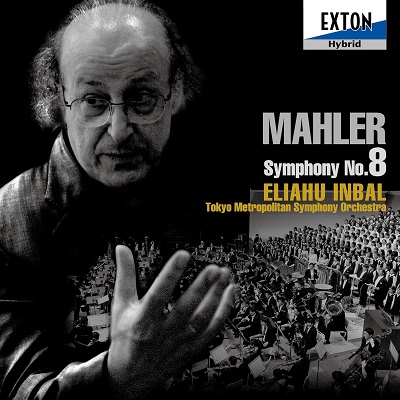別所憲法9条の会HP 《9j音楽ライブラリー》へリンク
GWを前にして、その人は天国へと旅立った。極楽往生と言った方が良いだろうか。飄々とした、穏やかな人だった。その人のことをなにからなにまで知っていたわけではないが、それなりにつきあいがあったので、善き人であることはわかっていた。悩み多き現世(うつしよ)を離れ、今頃は平安に包まれているだろう。
もとより罰当たりの無信仰者ゆえ、ふだんは死後の世界、天国も極楽も彼岸も気にかけたりしない私ではあるが、やはり死者の安息を願わずにはいられない。虹の橋を渡った先に懐かしい顔ぶれが待っているのなら、自分もことさら生に固執しない方が幸福かもしれない。ふと、そういう気持ちになりかけるのだが、「それで良いのか」という声に呼びとめられる。
「もうすることはないのか?」
「いいえ、でも私は疲れたのです」
「疲れているのはお前だけではない」
「私に何をせよと?」
「それは自分で考えよ。休息はその後だ」
幻聴だろうか、それとも内なる声…。一神教の天国は、最後の審判を経て、善行のあった人間がだけが入ることを許された天上の理想世界。そこには神や天使がいて、霊魂が永遠の祝福を受けるところだとされている。仏教の極楽浄土も、苦のない安楽な世界だが、そこに神がいるわけではない。
どちらも生前の行いが良ければ救済の対象になり、良くない者は地獄ゆきになる。だから生きているうちに良いことをしましょう、悪事を働いてはいけませんよという戒めにもなっているのだろうが、天国に行きたい、地獄に墜ちたくない、だから善を積んでおこうって、先々のことを見据えた取り引きみたいだなぁ。トランプ流のディールってやつか?善をなすのは極楽行きのための手段とは違うと思うのだが、なにか合格するのが目的の受験勉強を連想しないか?良い行いが評価されてというのは、いわば結果のはずだが、より良い行き先のために対策だとしたら、まるで試験対策とか予備校ビジネスじゃないか。
とまあ、人は天国と地獄の分岐点でどうあるべきか、あれこれ考えてみたりもするわけだが、神道(明治以後の天皇教ではなく)の黄泉だけが少し違っていることに気づかされる。死者は生前の行いに関係なく、みな黄泉に行く。『古事記』では、そこは行きたくなるような場所としては描かれていない。そうした違いがあるものの、いずれもが死後にこの世とは違う世界に行くこと、つまり肉体とは別の霊魂の存在を前提にしている。どの宗教でも、たとえ無宗教であっても、やはり人は原始的なアニミズムを心の奥底で認めているということだろうか。
天国の門が開かれなくてもかまわない。自分は天国に入りたいわけではないし、行けるとも思っていない。そもそも無信仰者なのだし、善行を積んできたわけでもない。しかし、先に逝ってしまったものに二度と会えないというのは、やはり寂しいものだ。何か心の空隙を埋めるもの、癒やし、それらを欲するところが信仰につながっていくのだろう。
そう思っていると、風のささやき、鳥のさえずり、それらが慰めにも叱咤激励にも聞こえてくる。だが待てよ、他の人と共有するには音楽の方が相応しいかもしれない。生きていることへの感謝。あゝ、『テ・デウム』か。
『テ・デウム』は、アントン・ブルックナー(1824~96年)が1881年に作曲した、後期ロマン派で最高の宗教曲とも言われている作品。熱心なカトリック信者の作だけあって、敬虔な感情にあふれ、オルガン的な響きの豊かさがいかにもブルックナーらしい。演奏時間は30分ほどで、宗教曲としては短い方だが、ソプラノ、アルト、テノール、バスの独唱と混声合唱団を必要とする規模の大きなものだ。
::: C D :::
1)交響曲第7番ホ長調 〈ハース版〉
2)テ・デウム ハ長調

独唱:マーガレット・プライス(ソプラノ)
クリステル・ボルヒェルス(コントラルト)
クラエス・H・アーンシェ(テノール)
カール・ヘルム(バス)
合唱:ミュンヘン・フィルハーモニー合唱団
ミュンヘン・バッハ合唱団員
独奏:エルマー・シュローター(オルガン)
指揮:セルジュ・チェリビダッケ
演奏:ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1994年・ライブ(1)、1982年・ライブ(2)
ブルックナーを得意としたセルジュ・チェリビダッケ(1912~86年)。ルーマニアに生まれ、欧州、特にドイツで活躍した人である。1976年に名門ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者に就任すると、同楽団をドイツのトップクラス、いや世界的なオーケストラに押し上げた。このコンビは1986、90、92、93年の四回にわたって来日しており、その演奏曲目には必ずブルックナーが含まれていたはずである。
このCDは、交響曲第7番のカップリングとして『テ・デウム』が収録されている。どちらもライブなのだが、録音時期には10年以上の開きがある。『テ・デウム』は、一応書き上げられたのが1881年、今日演奏される形になったのは83年から84年である。交響曲第7番の作曲に着手したのも81年で、全4楽章が完成したのが83年であるから、この二曲はほぼ同時進行的に作られたと言えるだろう。実際、『テ・デウム』で使われた音型が交響曲第7番の第2楽章にも顔を出している。
ブルックナーはリヒャルト・ワーグナー(1813~83年)を敬愛していた。ちょうどこの時期、そのワーグナーが死去。この交響曲の第2楽章にそれが反映していると言われている。また、第7番以降の交響曲にワーグナー・チューバが使われるようになったのも、ワーグナーとワーグナーの死の影響だろう。第6番までの交響曲の初演は失敗続きだったが、第7番はどうにか成功裏に終わった。この作品を、当時の批評家たちはベルリオーズやリスト、ワーグナーの延長線上にあるものと受け取ったのだとしたら、たぶんそれは誤解だったと思う。
この第7番、どこかで耳にしたことがあると思った人もいるに違いない。ルキノ・ヴィスコンティ監督による1954年の映画『夏の嵐』の全編で流れているのだ。《映画の中のクラシック》で取りあげるべきだったのを、みごとに失念していた次第。
『テ・デウム』は神に感謝の心を捧げる讃歌であり、ワーグナーの“俗”に対し、ブルックナーらしく“聖”を感じさせるものだ。全体は五曲で構成され、第1曲「天主よ、われら御身をたたえ」の力強いアレグロで始められる。モデラートの第2曲「御身に願いまつる」では敬虔で表情豊かなテノールの独唱が、第3曲の「とこしえに得しめ給え」は合唱もまじえ、アレグロから速度を落としながら荘厳さを強調。第4曲「御身の民を救い給え」の前半はテンポも編成も第2曲と似ているが、ここではホルンが加わって合唱との対比を見せる。後半は力強いアレグロとなり、第1曲との関を見せる。第5曲「主よ、御身により頼みたてまつる」は四人の独唱に始まり、楽器を増やしながら進行。金管楽器群と合唱が重なり、広がっていく主題が第1曲の主題を回想するかのように力強く終わる。この複雑な調性だけはワーグナーを思わせたりもするのだが、まあ、今回はあまり深く詮索したりせず、与えられた音楽に心を委ねたい。
(しみずたけと) 2025.6.6
9jブログTOPへ
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ