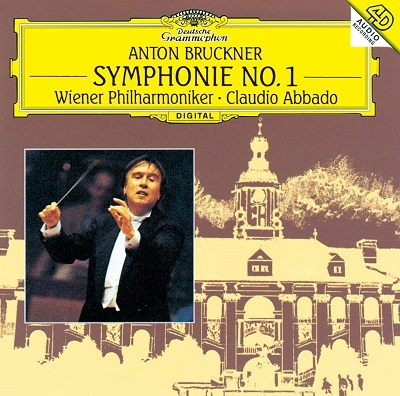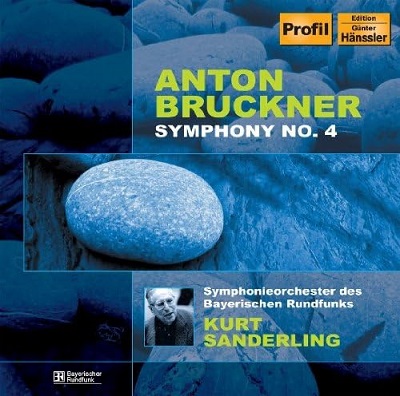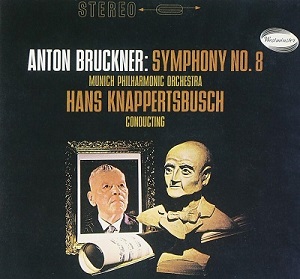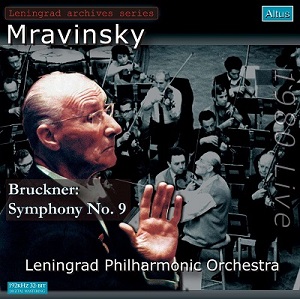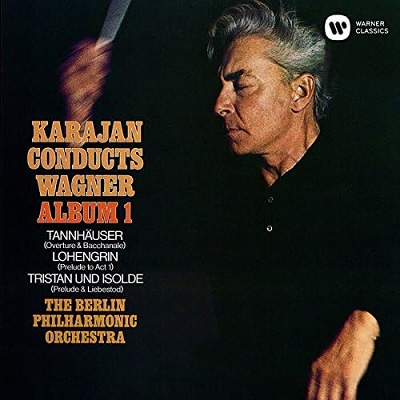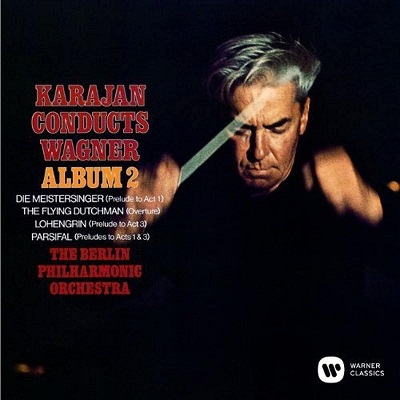別所憲法9条の会HP 《9j音楽ライブラリー》へリンク
ウクライナ戦争が始まって三年半。ふと思い出したのがこの序曲『1812年』。ピョートル・チャイコフスキー(1840~93年)が1880年に作曲したもの。大序曲とか祝典序曲と呼ばれたりするだけあって、とにかく派手な曲である。
1812年というのは、ナポレオンが〈大陸封鎖令〉を破ったロシア帝国に対し、20以上の民族、70万ものフランス帝国軍を率いておこなった遠征の年。ロシア側では〈1812年祖国戦争〉と呼んでいる。
緒戦はフランスの連戦楽勝。しかし制圧したモスクワはもぬけの殻。ロシア軍は街に火を放って退却していたのだ。戦闘は空振り。待てど暮らせど、ナポレオンに伺候するロシア貴族はやってこない。食料の現地調達にも失敗。そうこうしているうちに冬がやってきた。慌てて退却を始めたものの、防寒装備を持たないフランス軍は寒気にさらされ、そこへロシア軍がゲリラ攻撃。落伍者、逃亡者が続出し、今のベラルーシを流れるベレジナ川を渡った時には3万人弱、パリまで戻れたのは3,000人だったと言う。ナポレオンは以後、没落の道をたどることに…。
序曲『1812年』変ホ長調 作品49
チャイコフスキーはこの戦役を管弦楽化。五つの顕著な主題が使われており、ひとつはフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」。あとの四つはロシア聖歌やロシア民謡をもとにしたメロディで、これらが入れ替わりながら「ラ・マルセイエーズ」を圧倒、最後は沈黙させることで勝利を描くという描写音楽になっている。しかし「ラ・マルセイエーズ」がフランス国歌に制定されたのは1863年。ロシア国歌が作曲されたのは1830年なので、1812年には影も形も存在していなかった。こうしたちぐはぐさを抱えながらも、ロシアにとっては祖国防衛を音楽で表したシンボリックな存在となっている。
曲は長めの序奏、かなり自由なソナタ形式の主部、規模の大きいコーダという三部構成。ラルゴで始まる序奏の主部にはロシア正教会の聖歌「神よ汝の民を救いたまえ」である。最初はヴィオラとチェロのソロで、それから木管群と弦楽器群が交互に演奏し、強奏の後はオーボエ、さらにチェロとコントラバスが主題を受け継ぐ。低音楽器が終始主導するのは、迫り来るナポレオン軍への恐れを表しているのであろう。
つづく主部はアンダンテ。弱音で始まるティンパニーは軍鼓である。これに低音楽器群が加わり、次第に盛り上がっていく。ロシア軍の集結と進軍を表しているようだ。アレグロで奏られるボロジノ地方の民謡をもとにしたメロディは〈ボロジノの戦い〉である。ホルンによる「ラ・マルセイエーズ」の旋律はフランス軍の出現。最初は部分的にだが、徐々に長い旋律となり、金管楽器群によって反復されるが、木管と弦楽器によるロシア聖歌の主題がこれと絡み合う。ロシア民謡風の主題に引き継がれ、一方「ラ・マルセイエーズ」の主題は乱れがちにになり、大砲が五回轟くと、転がり落ちていくように収束していく。
再びラルゴに戻り、バンダ(別動隊)を含む全金管楽器群が冒頭の主題を吹奏、これに木管および弦楽器がかぶさり、勝利を告げるロシア正教会の鐘が鳴り響く。全楽強奏による壮大なアレグロ・ヴィヴァーチェ。戦勝を祝うかのような強奏。鐘と大砲の音を背景に、ファゴット、ホルン、トロンボーン、チューバ、低音弦楽器が奏でる重々しいメロディはロシア帝国国歌である。
1882年8月20日、この戦役で焼失したハリストス大聖堂の再建を祝う行事が開かれ、聖堂前広場で初演された。このとき、砲兵隊が実際に大砲を撃ったという。こういう曲であるから、野外で演奏される時には本物の大砲を使うことがお決まりになっているようだ。ロシアなら、戦勝記念日とか国家の式典などである。ロシア以外の国でも、軍事パレードなどで取り上げられることが多い。大砲の発射音が入っている曲などそうそうないし、実際に大砲を撃ってみたい軍隊と、それを喜ぶ戦争マニアやミリオタが集まるイベントには、これほどピッタリの作品はあるまい。日本でも、自衛隊が関わる式典で聴くことができよう。なお、フランスはこの曲をあまり演奏したがらない。
他の曲にはない、この曲ならではの特徴。それは大砲の“轟き”だし、それが入っていてこそ“らしい”と思う。しかし空砲であっても、録音スタジオやホールでは無理というもの。だから大太鼓を用いるか、別途収録した大砲の発射音をかぶせたり、最近ではシンセサイザーを使用する場合もある。大太鼓より大砲の方が迫力があるのは確かだが、本物の大砲となると、既に書いたように軍とか自衛隊の出番であり、そうした野外イベントがお似合いなのだと思う。
ロシアの戦勝を祝った曲であるという理由から、2022年に始まったウクライナ戦争により、この曲の演奏を取りやめる動きもみられた。この曲を否定するとか、作曲家やロシア音楽への反発ではなく、苦悩するウクライナの人々への配慮、連帯のメッセージである。しかし、チャイコフスキーがウクライナにルーツを持つ家柄であることを思うと、いっそのことパロディとして、「ラ・マルセイエーズ」をロシア国歌に、ロシア国歌をウクライナ国歌とウクライナ民謡に置き換えた序曲『2022年』を、誰か書いてくれないものだろうか。そんなことを思ってしまう。
::: C D :::

人気の曲なので録音はかなりある。お気に入りの指揮者、贔屓のオーケストラで聴けば良いと思うが、大砲の実射音を期待するなら要検討である。軍とか自衛隊の協力を要請するとして、彼らが所有する大砲は現代のもの。そりゃそうだ。ナポレオンの時代は200年以上も前で、当時の武器が今も役に立つはずもなく、骨董品のような大砲を装備する軍隊などありはしない。年代物の大砲を置いているのは、せいぜい博物館くらいなものだ。
何が問題かというと、当時と今の大砲では発射音がまるで違うのだ。現役の大砲は、射程距離を伸ばすために砲身は長く、火薬の燃焼速度が速い。その違いがそのまま音に表れてしまうのである。実際、そうした現代の大砲による演奏や録音がないわけではない。自衛隊が協力した国内の演奏会では、155mm榴弾砲FH70や203mm自走榴弾砲M110、あるいは74式戦車の105mmライフル砲L7A1とか90式戦車の120mm滑腔砲L44が使われた。欧州のNATO軍の装備も日本の自衛隊とほぼ同じである。文字で表すのは難しいが、強いて書くとすれば「ズゥキューン」という音であろうか。それなら大太鼓の「ドーン」の方が良いとさえ思える。
ハンガリーの名匠、アンタル・ドラティ(1906~88年)。オーケストラ・ビルダーと呼ばれ、新楽団の創設や危機に瀕したいくつもの楽団を立ち直らせた実績を持つ。今日ミネソタ管弦楽団となったミネアポリス交響楽団もそのひとつである。この1958年の演奏は、録音技術にこだわりを持つマーキュリー・レコードのエンジニアが、陸軍士官学校からはフランスのドゥエーでつくられた1775年製12ポンド青銅製の大砲を借り出し、マンハッタンのリバーサイド教会の72個もの鐘からなるローラ・スペルマン・ロックフェラー記念カリヨンを使い、さらにはミネソタ大学のブラスバンドまで引っ張り出しておこなわれた。その甲斐あって、演奏も音質も圧倒的なものになっている。
出来映えのあまりの素晴らしさに、米国の作曲家ディームズ・テイラー(1885~1966年)による解説がつけられた。まるで英語教材のように聞き取りやすい英語なので、こちらも、ぜひ。LPレコードは、なんと200万枚も売れたそうだから、クラシック音楽のファンだけでなく、オーディオ・ファンがこぞって買ったのであろう。
カップリングの曲は、まずは同じくチャイコフスキーの代表作のひとつである『イタリア奇想曲』。純音楽的には『1812年』よりはるかに優れた作品だと思うのだが、いかんせん、あのど派手な『1812年』の後に聴くと、なにやら物足りなく感じてしまう。LPにしてもCDにしても、商品化のための曲の組み合わせは難しいものだ。
もう一曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827年)の『ウェリントンの勝利』である。こちらもナポレオン戦争が題材。1813年6月21日、スペインにおける〈ビトリアの戦い〉で、ウェリントン侯アーサー・ウェルズリー率いる英国軍がフランス軍に勝利したことを受け、ウェリントン侯を讃える曲としてベートーヴェンが作曲したものである。
前半は戦闘の様相。左右から聞こえてくる行進ドラムと進軍ラッパは、それぞれ英国軍とフランス軍。やがて「ルール・ブリタニア」と「マールボロ行進曲」のぶつかり合いになり、短調にアレンジされた「マールボロ行進曲」の収束がフランス軍の撤退を表す。後半はデフォルメされた英国国歌をまじえた英国軍の勝利を祝う華々しい凱歌。「戦争交響曲」と呼ばれたりもするが、描写音楽であり、ベートーヴェンの交響曲に含まれることはない。本演奏ではマスケット銃が使われている。
収録曲
1.チャイコフスキー:祝典序曲『1812年』作品49(1880年)
2.チャイコフスキー:イタリア奇想曲 作品45(1880年)
3.ベートーヴェン:ウェリントンの勝利(戦争交響曲)作品91(1813年)
指揮:アンタル・ドラティ
演奏:ミネアポリス交響楽団(1-2)
ミネソタ大学ブラスバンド(1)
ロンドン交響楽団(3)
録音:1955年(2)、1958年(1)、1960年(3)年
(しみずたけと) 2025.8.31
9jブログTOPへ
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ