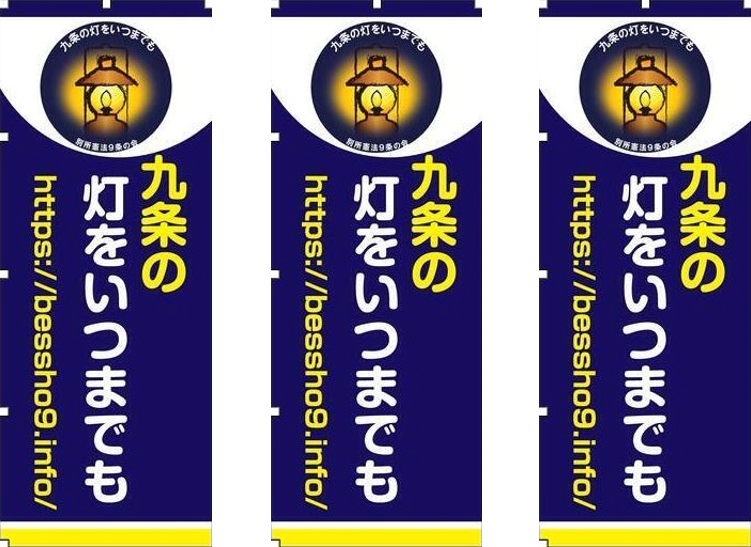
行政が住宅街に設置したスピーカーから、なにやら音声が流れてきた。反響がひどく、実に聞きづらい。どうやらJアラートの試験放送のようだ。「だから何?」「どうしろ?」というのか。
北朝鮮から弾道ミサイルが日本めがけて飛んできたとして、私たちは何をすべきか、何ができるのか。わが家には核シェルターも地下室もない。わが家だけではない。ほとんどの家がそうだろう。避難しろ?いったいどこへ?頭を抱えてしゃがみ込むくらいなものだ。まったくバカバカしい。
このバカバカしさにつき合って、ついでに少し考えてみることにした。たとえば、日本は海に囲まれており、その海に面して原子力発電所およびそれに類する施設がずらり、18箇所に57基。この中には停止中、あるいは廃止措置中の発電所や炉もあるが、内部に核燃料を抱えたままである。他に、やはり廃止される高速増殖原型炉と新型転換炉原型炉があるが、建設中の3基、六ヶ所村の再処理施設ともども、この数には含めていない。
海から丸見えのこれらの施設に攻撃が加えられたら、たとえ通常兵器によるものであっても、核攻撃と同じ結果になる。いや、貯蔵されている核燃料の量を考えると、核ミサイルよりもはるかに甚大な被害をもたらすに違いない。冷却水の取水口を破壊されただけで、冷却機能を失った炉は暴走、メルトダウンするだろう。内部に爆弾を抱えているのも同然だ。
国家間紛争の解決手段として、わが国は戦争という手段を、そもそも想定していないのである。憲法9条の問題ではない。日本の社会、経済や産業構造自体が、“戦争がない”ことを前提にしているのだ。政府は軍事力による国防を推進したいようだが、そうであれば一刻も早く脱原発を実現しなければならない。原発の再稼働だけでは飽き足らず、さらに新規建設など、二兎を追う矛盾にみちた政策に、みな気がつかないのだろうか。
抑止力という言葉がある。飛来するミサイルを撃ち落とすとか、そういうイメージを抱く人が多いかもしれない。最近では“敵基地攻撃能力”とか言いだした。発射されたミサイルを確実に迎撃できるか不安だから、発射される前に、発射されそうになったら、その兆候があれば…、こちらが先に攻撃してしまおう、「攻撃は最大の防御なり」というわけだ。
これはもう、防衛などではない。先制攻撃そのものである。あまりに露骨であることに気づいたのか、あわてて“反撃能力”と言い換えたりしている。しかし、変わったのは言葉だけらしい。攻撃もされていないうちに攻撃するのを反撃とは呼ばない。
抑止力、英語ではdeterrenceという。deter、「…するのを思いとどまらせる」という動詞から来ている言葉である。つまり、攻撃することを思いとどまらせる、攻撃させないというのが本来の意味であって、攻めてきた敵に対処するとか迎え撃つということではない。攻めさせない、それこそが抑止力である。
北朝鮮との関係を考えてみよう。あの国と日本の間に領土問題は存在しない。互いの国土に対して領有権を主張しているのでもない。北朝鮮には日本を攻撃する、これといった理由がないのである。それとも、北朝鮮が日本の全土あるいは一部を支配しようと企んでいるとでも思っているのだろうか。
次に何のためのミサイル発射なのかを考えてみる。挑発行為と捉えられているが、日韓や米国を挑発し、軍備増強の必要性を実感させることが目的ではないだろう。国家予算が有り余っていて、それを軍事費につぎ込むことで消化しているのでないことも、いまさら言うまでもない。北朝鮮にとって、核開発やミサイル発射実験は、まさに抑止力なのだ。攻めてきたら反撃するぞ、こちらには核もあるぞ、そちらもただではすまないぞ、だから攻めてくるなよというメッセージである。
北朝鮮の抑止力に対して、なぜ私たちは恐れるのだろうか。もしかしたら先制攻撃してくるのではないかという不安感があるからだと思う。先に攻撃しない、専守防衛に徹することを国是とする国であれば、このような恐怖心を抱かずにすむはずだ。つまり、北朝鮮には憲法9条がないからである。
相手に攻撃させない、正しい意味での抑止力を発揮するために必要なことは何か。今年の憲法大集会で、中野晃一さんは、reassurance、“安心供与”という言葉を使っていた。「安心させる、再保証する」という動詞reassureを、さらに分解してみよう。「保証する、請け合う、確信させる」を表すassureに、「再び」の意味を持つ接頭辞のreを付け加えた言葉であることがわかる。
先制攻撃したりしない、先に手出ししない国であることを、他国に「あらためて確信してもらう」。軍事力行使より前の段階でこそ必要なこと、これこそが抑止力なのである。今の時代、どの国も領土拡張や他国の支配を掲げて戦争を始めたりしない。いつだって自国民保護、領土保全、自国の安全保障のためであり、防衛のためにやむなく…という理由で戦争を始めている。
日本は「戦争しない」ことを世界に向けて宣言した国である。9条だけでなく、憲法の前文でそれを謳っている。これこそが、世界で五本の指に入る軍事力を保有しながら、他国に対するreassurance、信頼の担保になっているのである。自分たちが戦争を始めないというだけでなく、相手に戦争の口実を与えない、最大の抑止力であることに気づくだろう。実に賢い手段だと言えないだろうか。
これまで「こちらから先に手出しすることはありませんよ」という看板を掲げていた日本が、憲法改定によって、その看板を下ろしてしまったらどうなるか。周辺国は戦々恐々だろう。なにしろ、心にもない大東亜共栄とかを標榜し、軍事力で朝鮮を併合し、中国に攻め込み、アジア中を戦場にした過去を持つ国である。私たち日本国民が思っていなくても、「いよいよ戦争を仕掛けるつもりになったのか」と受けとられかねない。
世の中に“ならず者”がいるように、世界には“ならず者国家”が存在する。彼らには理性や道徳的観念などなく、こちらの論理は通じない。戦争の口実は、見つけるものではなく、こしらえるものである。そうした国に対処するには軍事力しかない。そう考える人もいるだろう。しかし、それは現実的だろうか。
飛来したミサイルを空中で撃ち落とす。相手は当然、撃ち落とされないミサイルを開発することになる。こちらは、それをまた撃ち落とすシステムを作るしかない。すると相手は…。莫大な費用を投じて開発した兵器も、すぐに旧式化、陳腐化してお払い箱になる。双方が終わりのない軍拡競争を続けることになるのだが、その財源はどうするのか。
国家に打ち出の小槌、ドラえもんの四次元ポケットがあるわけでなし、軍事への支出を増やせば、他を削るよりほかはない。消費税のアップ、福祉の切り捨て、年金の減額ないし支給対象者の絞り込み、医療費の負担増、教育は無償化どころか、むしろ義務教育の有償化も検討事項になるかもしれない。いつ攻めてくるか、攻めてくるかどうかもわからない敵に備え、国民は窮乏生活を耐え忍ぶことになる。軍事大国の国民は苦しい生活を強いられるのが常だが、そんな日常を選択してまで、軍事力にすがりたいものだろうか。
私たちが“ならず者国家”だと考える国は、たいていは民主主義が実現されていないか、低レベルに留まっている国だろう。民主主義と呼ばれる国であっても、国民の声がすべて政府に届くわけではないが、権力政治が行われる国ではなおさらだ。しかし、軍事政権や独裁政権の国であっても、すべての国民がそれに共感しているわけではない。理不尽な国家権力を打ち倒そうとする勇気ある人々と手を取り合うことが求められているのである。
軍事力は、金ばかりかかって、本当に役に立つかどうかもわからないし、そもそも本質的な問題解決を目指していない。世界に不安と脅威を振りまく権力政治を民主主義へと転換させることは、それらの国の人々を恐怖と欠乏から解放し、自由をもたらすとともに、“ならず者国家”をなくし、結果的に私たちの安全につながるだろう。平和で争いのない“もうひとつの世界”の構築は、実は日本国憲法の理念そのものである。その憲法を、日本が捨て去ることは、世界の良心を裏切り、未来への希望を遠ざける行為になる、私にはそう思えてならないのである。
(しみずたけと) 2022.5.27
「こちらから戦争を仕掛けることは絶対に絶対にないよ!」と言う、今掲げている看板を取り下げることは、他の国に「やっぱりね! 思ってたとおりじゃん! 日本は全然変わらなかった。」と思われるってこと。そうしたら、戦後のこれまでの数十年は霧散してしまう。わたしたちは再び戦争に巻き込まれる。まさに、「巻き込まれる。」戦争をしたい人はほんの一部だから。
お金のことを言えば、お金は上手く使えば人々を幸せにするのに、どぶに捨てるようなことに躍起になっている人たちは何を考えているのだろう? あ、どぶに捨てるんじゃなくて、自分のふところに入ってくるようにする、または、自分の権力を増大させるのに使うってことかな。 Ak.