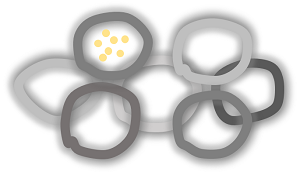
オリンピックをめぐる二つの発言から見えること
東京オリンピック閉会から二ヶ月、パラリンピックが終わって一ヶ月が過ぎた。まだ…なのか、もう…なのか。開催か中止かであれだけ大騒ぎしたにもかかわらず、今や誰も話題にしない。あれはいったいなんだったのだろうか。検証すべきことは多々あるが、ここでは気になった二つの発言をとりあげたい。
7月28日のテレビ朝日《モーニングショー》で、アナウンサーの羽鳥慎一氏が、米国を破り金メダルを獲得したソフトボール日本代表選手に、「本当に素晴らしいプレーでした」とたたえた。
このことに対し、作家の百田尚樹氏がツイッターで、「まず最初に、『皆さんの活躍の場を奪うために、五輪開催に反対して、すいませんでした』と謝ってから、インタビューしろや。クソモーニングショー!」と批判。「『五輪反対と選手応援は別』というのが、五輪反対を唱えていたメディアやエセコメンテーターの言い分だが、こんな欺瞞はない!彼らは選手たちの活躍の場を奪う為に、なりふり構わず開催に反対してきた。メダリストを応援するなら、まず自身の発言を総括してからにせよ!」というわけである。
どこがおかしいか、もうお気づきだろう。多くの人が、新型コロナの感染拡大を危惧し、オリンピックの中止ないし延期を訴えた。それは、アスリートの活躍の場を奪うためだったのか?大会中止になれば、彼ら・彼女らの活躍の場が失われるのは、その通りだ。しかし、それは結果としてそうなったとしても、活躍させないことを目的としたものではない。
春から夏にかけ、外出の自粛が呼びかけられ、飲食店は時短営業が要請され、学校は休校になった。それは飲食店を廃業に追い込むためだったのか?子どもたちの学習機会を奪うことが目的だったのか?そうではあるまい。これらの有効性、適切な措置だったのかは議論の余地があるとしても、あくまでもコロナの感染拡大を防ぐための対策だった。オリンピック開催か否かの問題も、まさにそこにあったはずである。
こんな簡単な論理が、文筆を生業にする百田氏にわからないはずがない。私は氏の著作は『永遠の0』しか読んでいないのだが、半世紀も前からある元零戦パイロットの著書や空戦記録、たとえば坂井三郎氏の『大空のサムライ』などを上手に換骨奪胎、実にみごとに自著に取り込んでいるところなど、なかなかの知性だと感心させられてきた。モーニングショー批判が、論理の飛躍というよりは、別の事柄の無理なこじつけであり、批判を目的とした論点のすり替えであることくらい、百も承知だったはずである。
もうひとつは、「バッハ高笑い」と題した週刊誌『女性自身』の記事に対する、脳科学者の茂木健一郎氏のツイート。
オリンピック開催前のアンケートでは、「楽しみ」が16%、「始まれば楽しめそう」が31%だったが、開幕後は日本人選手のメダル・ラッシュもあり、「開催してよかった」が77%に。その結果が「バッハ高笑い」というタイトルになった。
茂木氏は、「バッハ高笑いというよりも、日本人たちはイデオロギーじゃないやわらかい心を持っているというだけのことだと思います」とし、日本人の柔軟性を強調したのである。
これを柔軟性というのだろうか。そういえば、戦前・戦中は「鬼畜米英」「出てこい、ニミッツ、マッカーサー 、出てくりゃ地獄へ 逆落とし」などと叫んでいたにもかかわらず、戦争に負けたとたん、ウィリス・ジープを追いかけながら「ギブ・ミー・チョコレート」を連呼した国民である。一億総玉砕を主張し、特攻隊という名の自爆テロを推進した人物が、お国のためにも、天皇のためにも、名誉のためにも死ぬことなく、戦後はアメリカ礼讃者に早変わり、総理大臣にまで登りつめたりしている。これも、イデオロギーとは無縁の“やわらかい心”のなせる技なのだろうか。
“やわらかい”という言葉には、“頑な”とか“頑固”“頑迷”とは逆の、好ましい側面を感じるものだが、それは“忘れっぽい”とか“流されやすい”と同じではなかろう。茂木氏は脳科学者なのだから、言葉を選ぶときに、その内包するモノを、もう少し細やかに意識してもらいたいところだ。
ちょっとした発言ではあっても、ふたりともオピニオンリーダーとして知られ、著名人であるから、その影響力は小さくない。百田氏の場合、いつもながらの荒い言葉遣いによるアジとは言え、安倍晋三元首相の、「一部オリパラ中止の声は反日的人物によるもの」という発言と同類である。よく考えない、流されがちな大衆をアジで誘導し、愚民が「そうだ、そうだ」「羽鳥はケシカラン」「テレ朝をブッつぶせ」となると、国民総出で戦争に突入していった戦前の世相とオーバーラップしてくる。そして、いったん始まってしまったら最後、肯定的な見方、都合の良い解釈しかできなくなってしまい、方針の転換もやめることもできなくなってしまうところも、あの頃と変わっていない。
必要かどうかの疑問が生じても中止できないダム建設、トンネル工事、リニア新幹線、原発…。中央卸売市場の豊洲移転、経営破綻まで突っ走った山一証券にも言えそうだ。この国には政策の“修正”という機能が備わっていない。あるのは、歴史修正主義という名の“思想の修正”だけである。それが恐ろしい。
(しみずたけと) 2021.10.15
“祭り”が幕を下ろしても…
どんな祭りでも、必ず終わりはやってくる。開催が一年延期されたTOKYO 2020とは、いったい何だったのだろうか。
2020年夏の五輪大会の開催地が東京に決まったのは、13年9月のIOC総会。決定に先立つプレゼンテーションで、安倍晋三首相(当時)は、原発事故の状況について「アンダー・コントロールだと保証する」と発言した。だが、増え続ける汚染水を貯蔵しきれなくなり、政府と東電の方針は海洋放出である。まさに嘘による招致で勝ちとった開催だった。
東日本大震災による仮設住宅暮らしの人がまだ残り、広大な帰還困難区域を残したままの現状に、「五輪どころではない」「復興が先だ」という反対の声も多かった。そこで生み出されたのが“復興五輪”というスローガン。「五輪によって復興に弾みをつける」「復興のために開催する」というわけである。しかし、いつのまにかしぼみ、やがて消えていった。実際、工事は被災地から五輪関係にシフト。土建業者にとっては、国立競技場の建て替えや選手村建設の方がうま味のあるビジネスだったのだから、当然の帰結である。環状二号線の延伸が絡んだ築地市場から豊洲市場への移転問題も、その一環だった。こういうのを方便と呼ぶのだろうか。最終的に“無観客”となったこともあり、国内外から被災地に足を運ぶ人もおらず、認知される機会もなくなった。“復興五輪”は名実共に雲散霧消したわけである。そういえば、豊洲市場の土壌汚染問題はどうなったのだろう。
メイン・スタジアムとなる国立競技場の建て替えに目を転じてみよう。12年11月、新・国立競技場のデザイン・コンペで、ザハ・ハディッド氏の案が採用された。二本のキール・アーチを有する独特なデザインが注目されたものの、工期の長さや総工費が問題となり、開閉式屋根の設置を五輪後に先送りしたり、8万席のうち15,000席を仮設にし、五輪後に撤去するなどのコスト削減案が提案され、予定通り15年10月の着工が確認されたのだが、その3ヶ月前になって突如、安倍首相が白紙撤回を表明。再コンペによって、大成建設・梓設計・隈研吾氏らによる案が採用され、一年遅れの16年12月に着工、19年11月に竣工した。
新国立競技場では、開閉式屋根の設置は見送られ、屋根は観客席の上部のみ。暑さ対策に問題があると指摘されたが、無観客開催となったことが幸いして、問題は起きずにすんだ。そもそも、1964年の東京五輪のメイン・スタジアムを取り壊す必要があったのか。改修による近代化は不可能だったのか。想像するに、旧国立競技場の座席数(約55,000)では足りない、もっと多くの観客を入れたい、そういう商業的理由だったのだろう。無観客により、取らぬ狸の皮算用そのものというオチである。着工が遅れ、新国立競技場は2019年9月のラグビーワールドカップには間に合わなかった。なお、建設計画がキャンセルされた翌年3月、ハディッド氏は心臓発作により急逝(享年65)。憤死だったというつもりはないが…。個人的には、氏の建築デザインは好きになれなかったが、決定した側にこそ問題がある。
夏の東京の暑さに触れたので、そのことも考えてみたい。1964年の東京五輪の開会式は10月10日であった。これを記念し、国民の祝日として《体育の日》が制定(2020年に《スポーツの日》に改められている)されたわけである。あれから半世紀、人口増加、地表はアスファルトで覆われ、エアコンなどの熱源も加わり、東京はヒートアイランドと化した。以前より暑くなっていることは周知の事実。それにもかかわらず、7月下旬の開会だと? 13年1月、IOCに提出した日本の《2020年東京五輪誘致提案書》に、「この時期は温暖で晴天の日が多く、選手たちが自分の力を思う存分発揮できる理想的な気候を提供する」とある。みな、耳を疑ったはずだ。「夏の東京の暑さを知らないのか?」「熱中症で、選手だけでなく観客にも死者が出る」ともいわれた。宣伝文句が事実かどうかを自分で調べないIOCや各国選手団にも問題があろうが、「アンダー・コントロール」に続く嘘・第二弾であることは、今や世界中が知っていることだ。日本国民は平気で嘘をつく民族…。
暑さ対策として、マラソン会場が札幌に変更され、小池百合子都知事が「合意なき決定」と激怒する一面もあったが、競技後に札幌も東京と大差ないことがわかった。無観客が熱中症対策になったかどうかは不明だが、沿道で観戦する人の“密”が問題となった。競技場や体育館で観戦できない以上、テレビ観戦に飽き足らない人がマラソンや自転車ロードレースのコースに集まるのは当然である。観戦が感染を拡大していった。
時間を少し戻してみよう。2015年7月、クリエイティブ・ディレクターの佐野研二郎氏のデザインが大会の公式エンブレムに選ばれた。ところが、これがベルギーのリエージュ劇場のロゴの盗用ではないかと指摘され、使用中止が決定。再選考で野老朝雄氏デザインに決まったのは翌年4月である。
東京五輪招致をめぐる贈収賄の容疑で、仏捜査当局は2018年12月、招致委員会理事長(当時)の竹田恒和JOC会長の捜査を開始。竹田氏は疑念を残したまま、任期満了となる翌年6月に退任したが、18年から20年度の三年間の弁護費用が約2億円に上り、その全額をJOCが負担していることがわかった。JOCは3月の理事会で、捜査終結まで費用負担を決議しているのだが、そのカネはいったいどこから出るのか?
つづいては、 21年2月に「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」などと発言した組織委会長だった森喜朗氏。辞任を否定しながら、記者の質問を「面白おかしくしたいから聞いているんだろ?」などと発言し、火に油を注ぐことに。約一週間後に辞任を表明し、後任に指名された川淵三郎氏も、一度は受け入れたものの、密室人事との批判を受けて辞退。けっきょく橋本聖子氏が就任することとなり、五輪相の椅子が転がり込んだのは丸川珠代氏だった。
4月には、クリエイティブ・ディレクターの佐々木宏氏による演出プランが、タレントの渡辺直美さんをブタとして演じさせるものであることを、週刊文春がリーク。人の容姿を侮辱するものだとして問題化し、辞任に追い込まれた。ブタやブタの鼻の絵文字を使って「オリンピッグ」と表現する、なんともまあ低次元の駄洒落も検討されていたというから、いったいどこがクリエイティブなのだか…。
開会式の楽曲を担当する小山田圭吾氏が、小学校から高校時代に、障がいのある同級生に対するイジメを自慢げに語るインタビュー記事が注目を集め、7月19日に辞任を表明。組織委は同氏の楽曲を使わないことを決めた。
ようやく開会式と思いきや、前日に開閉会式のディレクターを務めるコメディアン、小林賢太郎氏が過去に、ホロコーストを揶揄する「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」なるパフォーマンスをおこなっていたことが発覚し、ユダヤ系人権団体が反発、解任となった。
五輪開幕後のコロナ感染急拡大については、今さら語る必要もないだろう。大会関係者、選手にも感染者があらわれ、選手村でクラスターも発生している。一般市民と接触させない“バブル方式”も機能不全だ。たとえば、ボランティアのタクシー運転手は、彼ら・彼女らの求めに応じ、エスニック・レストランやショッピング街へとクルマを走らせ、否応のないルール破りに加担させられている。
五輪開催の陰で、コロナ禍はどうなっただろうか。病床が逼迫し、政府は中等症患者は自宅療養だと言い出す始末だ。自宅療養でコロナが治るわけもなく、単なる放置に過ぎない。デルタ型変異株は病状悪化の進行が速く、中等症から重症へはすぐだ。その際、すぐに救急搬送が可能なのだろうか。また、受け入れ先はあるのだろうか。東京都では、8月に入ってから5日間で8人の自宅療養者が亡くなった。コロナ以外にも、心筋梗塞や脳卒中、交通事故など、素早い処置が生命を左右する病気やケガは少なくない。それらにも影響を及ぼすケースが心配になる。お産で死ぬような人が出たら、いったいどこの国の話だと思うが、それが今の日本である。
五輪を中止するチャンスはあったはずだ。アントニオ・グテーレス国連事務総長が、新型コロナ禍を「戦時中」との見解を表明したとき、開催中止を求める国際世論を味方につけることによって、違約金なしに取りやめることも可能だったかもしれない。その選択肢を捨てたのはなぜだろうか。けっきょく、菅義偉首相の「人類(の欲望)がコロナ(という恐怖と理性)に打ち勝った証」を地で行くことになった。
祭りが終わっても、すべてがチャラになるわけではない。パンドラの箱は開けられてしまった。後に残るコロナの大渦巻きと巨大な赤字。祭りの主催者が、反省したり、責任を取ることはないだろう。そのツケは、「メダルだ!」「感動した!」と浮かれていた人にも、そうでない人にも、等しく降りそそぐことになる。そのために生じる新たな亀裂。新国立競技場の建設によって、都営霞ヶ丘アパートの住民らは強制退去された。人々を分断することになった前代未聞だらけの五輪を、私たちはどのようにふり返るのだろうか。
(しみずたけと) 2021.8.8

