グスタフ・マーラー
交響曲第5番嬰ハ短調

「生は暗く、死もまた暗い」。グスタフ・マーラー(1860~1911年)の声楽を伴った交響曲『大地の歌』に現れるフレーズである。現代世界で、今の日本で、このペシミスティックな言葉がふと脳裏をよぎるのは、はたして私だけであろうか。
後期ロマン派の交響曲作家として人気のグスタフ・マーラー。今日ではオーケストラ演奏会でもしばしば採りあげられるメジャー作品になっているが、一昔前まではかなり特殊な扱いだったように思う。6本とかそれ以上のホルンなど、大編成でなければならないし、そのうえ難しいとくるのだから、高い水準の四菅編成楽団でなければ演奏できなかったのであろう。3番や4番、『大地の歌』は声楽ソリストが、2番や8番はさらに合唱まで必要とし、コストの問題もあったに違いない。私が初めて聴いたのは、1972年に日本フィルが解散する折りの最後の演奏会、小澤征爾が指揮する第2番『復活』のFM放送だった。正直なところ、複雑すぎて良くわからなかったのだが…。
当時のオーケストラが演奏する交響曲は、ベートーヴェンやブラームスなどの“ドイツもの”が多く、せいぜいチャイコフスキーまでが定番だったと思う。来日するオーケストラの場合も同じで、あとはフランスの楽団なら、ベルリオーズ、チェコならドヴォルザークと、いわゆる“お国もの”が採りあげられるくらいだった。それがいつしかマーラーを軸にしたプログラムがごく普通に組まれるようになったのは、ゴージャスで迫力ある響きを求める聴衆と、オーケストラの演奏技術向上、そして経済的安定のたまものではなかろうか。
ここで紹介する交響曲第5番は、第4楽章アダージェットが、ルキノ・ヴィスコンティの映画『ヴェニスに死す』で使われたこともあり、マーラーの交響曲の中ではそれなりの知名度はあった。その静謐感にみちあふれた美しい旋律は、実に心地よい。しかし、私にとって印象的なのは、第1楽章、とりわけ冒頭に奏でられるトランペットの不吉なファンファーレに始まる《葬送行進曲》につきる。交響曲に葬送のメロディが現れるのは、なにもこの曲だけではないのだが、冒頭に置かれたところに衝撃がある。
マーラーの演奏で、私の世代が真っ先に思い浮かべるのは、おそらくレナード・バーンスタインとゲオルク・ショルティの二人だろう。音作り、演奏スタイルはまったく異なるが、どちらも作曲者と同じユダヤの血を引いている。ウィレム・メンゲルベルク、ブルーノ・ワルター、オットー・クレンペラーといった、生前のマーラーを知る人たちを第一世代とするなら、第二世代ということになる。ここに採りあげたヘルベルト・フォン・カラヤンも、その中に含めてよかろう。
20世紀半ばのクラシック界に君臨し、幅広いレパートリーを手掛けたカラヤンであったが、マーラーを採りあげるようになったのは、かなり後になってからのことである。この第5番の録音は1973年、65才の時だ。ワルターやジョン・バルビローリの演奏で、既にマーラーは有名になっていたし、バーンスタインやショルティ、ベルナルト・ハイティンクは交響曲を全集録音していた。大編成のワーグナーや複雑精緻なリヒャルト・シュトラウスを得意としていたカラヤンが、スペシャリストではないにせよ、なぜマーラーをレパートリーの範疇外に置いていたのか。
第二次大戦中、指揮者のポストを得るためにナチス党員となったカラヤン。ユダヤ人音楽家への差別政策の加担者と見なされたことを理由にあげる人がいる。曰く、ドイツ楽壇の頂点を極めようとしていた彼にとって、マーラーを演奏することは自己否定につながるのだと。しかし、ユダヤ系の作曲家はいくらでもいる。カラヤンが交響曲を全曲録音したフェリックス・メンデルスゾーンもそのひとりだ。彼は、自身がマーラーを演奏するための機が熟すのを待っていたのではなかろうか。
カラヤンは、どんな作品であっても、その音と表現を徹底的に磨き込まずにはいられない完璧主義者だったし、独自の美学を持っていた。作曲家の感情移入が激しすぎるマーラーの作品は、あまりに生々しく、シェフにとって料理しづらい、アクの強い食材だったのだと思う。じっくり観察し、最良の調理法を編みだし、手兵ベルリン・フィルの演奏技術が十分な水準に達し、自分と楽団が最良の関係に昇華する時機、さらには納得いく録音技術の到来を読み切ったうえでの着手だったに違いない。最初に交響曲第5番が選ばれたのは、これが純粋な器楽曲だったからであろう。しかも、世に出たのは収録してから二年も後のことだった。甘く美しいだけでなく、冷静に計算されつくした、きわめて精妙かつ密度の濃い響きに仕上げられている。
冒頭のトランペットを吹くのは、ベルリン・フィルの奏者ではなく、当時10代の天才少年トランペッターだという。そのフレーズの美しさ、そして不思議な印象。他のどの演奏とも異なる、カラヤンならではの奥深い耽美主義とでもいえば良いだろうか。このメロディは、肉体の葬送なのか、それとも精神のそれなのか、はたまた社会を示しているのか…。ベルリン・フィルの機能美が可能にした、クライマックスへとつづく重層的な音響。それらは、もしかしたらマーラーの本質とは乖離したものなのかもしれない。そうした一抹の不安と同居する充足感。それゆえ、この演奏は、ある種の異端であり、現代におけるマーラー解釈にとって避けられない問題を投げかけているようでもある。
マーラーとカラヤンによる葬送行進曲は、われわれをどこに連れて行ってくれるのだろう。
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1973年
映画紹介
(しみずたけと) 2021.5.24
9j音楽ライブラリーに跳ぶ
リンク先は別所憲法9条の会ホームページ
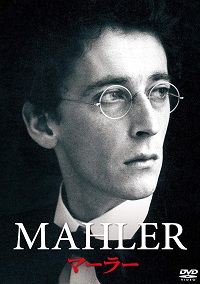

「マーラー 交響曲第5番」への1件のフィードバック