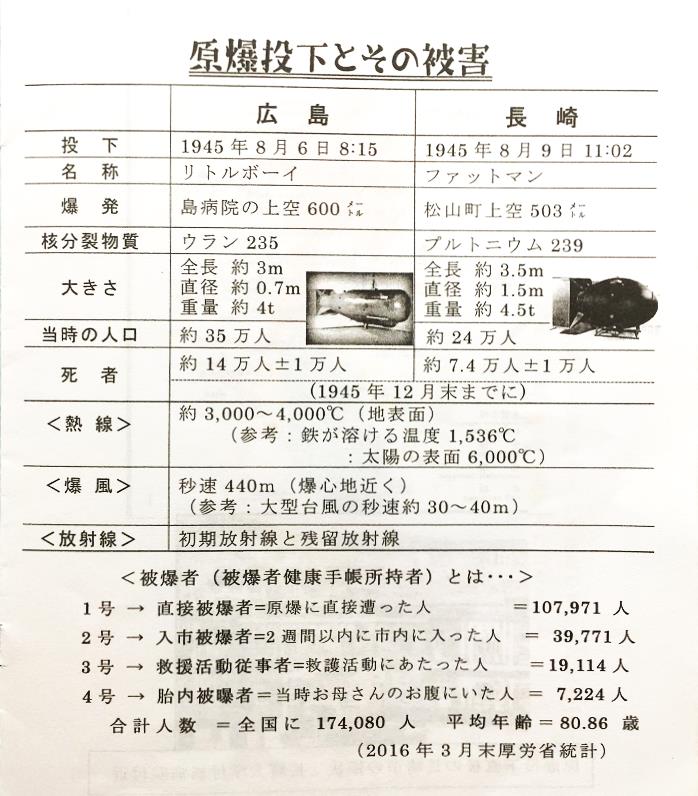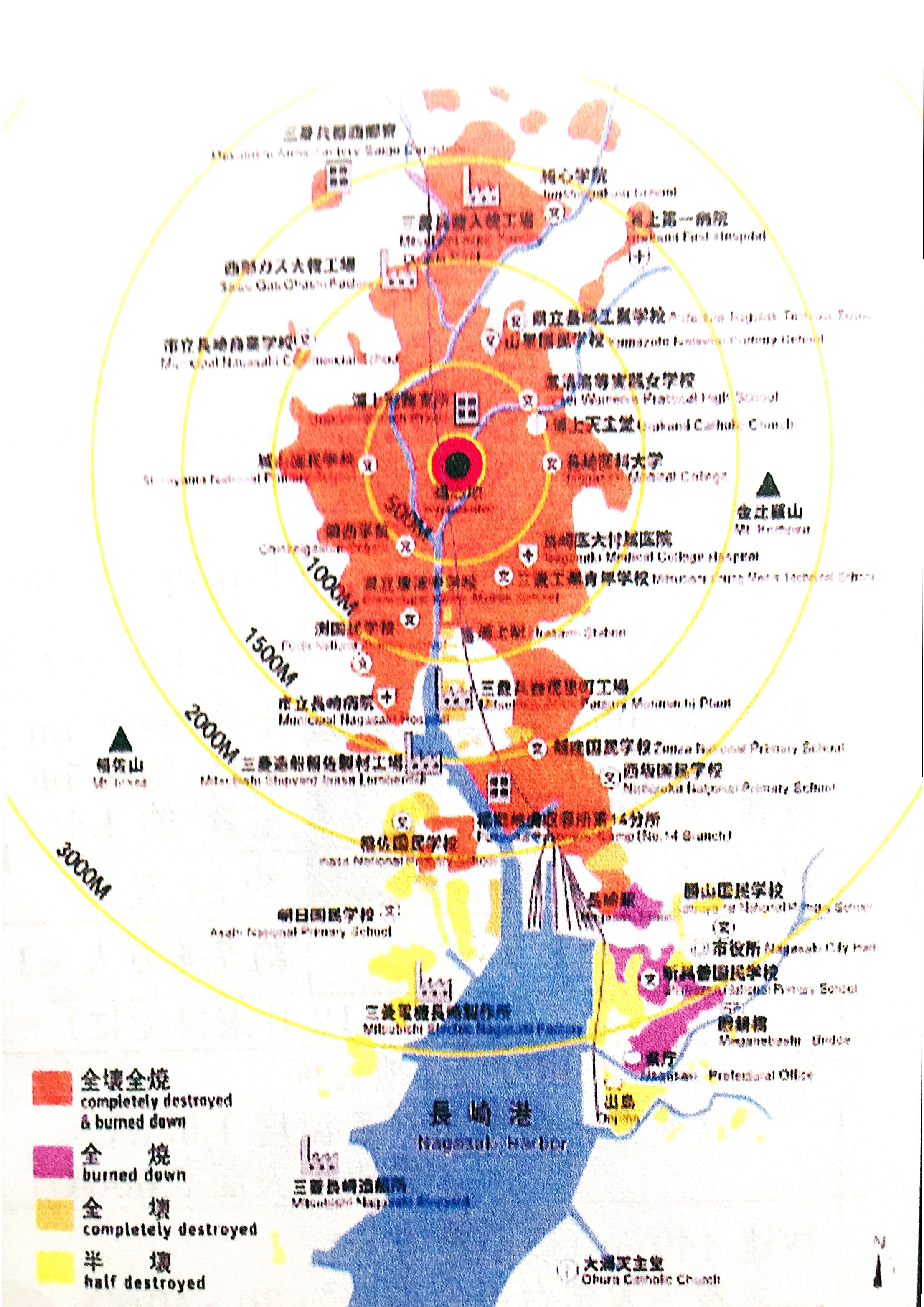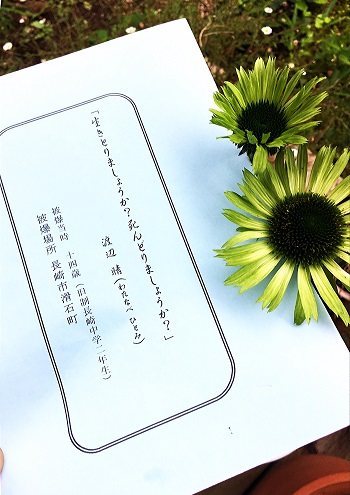
「生きとりましょうか? 死んどりましょうか?」
渡辺 睛
被爆当時 十四歳 (旧制長崎中学二年生)
被爆場所 長崎市滑石町
その日
昭和二十年(一九四五年)八月九日、午前十時ごろから自宅より五百メートルくらい離れた平宗川で泳いでいました。この川、今は滑石排水路と呼ばれていますが、一時間ほど泳いでいて、そろそろ午後一時から始まる軍需工場へ行く用意をしなければ、という時間になりました。これで最後にしようと思って川の土手から飛び込みをしようと身構えた瞬間のことでした。大きな爆発音と共に高熱が私の背中を襲いました。そして、強烈な風で私は川の中に吹き飛ばされていました。
幸いにも大火傷にならずに、水ぶくれ程度の火傷でしたが、皮膚がヒリヒリ痛むので、母がその後毎日スイカの皮で拭いたり、アロエの皮で拭いたりしてくれました。おかげで、蠅がウジ虫を産んで...というようなことにはなりませんでした。
それから三、四日して海軍病院の軍医さんが国鉄の道ノ尾駅前に来ましたので、列をなして診てもらいましたが、「火傷二度」と言われたのみで、薬ひとつ付けてくれませんでした。他にもっとひどい火傷の人とかがいたからでしょう。九月ごろには傷みも止みましたが、四十歳くらいまで、痕跡が残っていました。
川から急いで家に帰る道の途中にある藁葺きの農家が二軒、燃えていました。家に帰ると、家中の障子やガラス窓は粉々に壊れ、畳の上は飛び散ったガラス片でいっぱいでした。当時大学に行っていた兄が帰ってから一緒に片づけようとそのままにしていましたが、その夜は長崎の市内に帰れない人たちが、十人くらいでしょうか、板張りの床にごろ寝をしていました。
私の家は長崎の市内中心部から三、四キロ北へ離れていましたが、夜になって暗くなるにつれて、火が東の方へ燃え移る様子がわかって来ました。停電になっていたので、ラジオも聴けなかったのですが、負傷者の話しや近隣の住民の騒ぎから、事の重大さがわかってくるにつれて、兄の安否が気がかりになってきました。
兄の死
翌日、夜明けと共に父が兄を捜しに出かけて行きました。父は町中を歩き回りましたが、歩く地面の熱さがとてもスゴかったと言います。兄は当時、大学の構内にいたとのことですが、兄の真っ裸の遺体を見つけた時の話しです。
十二、三人の学生たちがほとんど全裸の状態で固まっているところを見つけて、「ワタナベヒサシはどこにおりましょうか?」と父が尋ねたところ、「痛い、殺してくれ、モヒ(=モルヒネ)を打ってくれ。」と叫んでいた学生たちの一人が「そこら辺に居るでしょう。」と答えたそうです。それを聞いて父は「生きとりましょうか? 死んどりましょうか?」と言葉を返したそうですが、それに対する返事はなかったとのことでした。
父ひとりで兄の遺体を運んで来ることができず、いったん家に帰ったのですが、夕方になって日が落ちてから、父の案内で、私と母は兄に最後の面会をしに大学まで行きました。不通になった線路に沿っての道はつらく長い道でした。私は一升瓶に水をいっぱい入れて持ち、母が持ったものは洗濯した浴衣でした。
線路の両脇には戸板を日よけに立てて、傷ついた被災者が何カ所も固まっていました。あちこちから「水をください。」、「助けてください。」という叫び声が聞こえました。母が「水を少しずつあげなさい。」と言うので、私が持っている一升瓶から水を分けてあげたのですが、一人の男の人が「どうか私の命を助けてください。」と私の顔を真剣に見つめ、両手を合わせて来た時には、私は飛び上がって逃げてしまいました。真っ黒にすすけて腫れ上がった顔、目だけが異様に悲しみを帯びたあの顔は忘れることができません。
大学に着いて見た兄の顔は、薄く泥に覆われてはいましたが、負傷して全身火傷で悶死した顔とは思いもよらない安らかな顔でした。母はとめどなく涙を流しながら持って来た浴衣を兄に着せました。
次の日は早朝から、父は兄を荼毘にするために叔父と一緒にまた大学の構内へ戻って行きました。その途中、アメリカ軍のグラマン戦闘機の機銃掃射に出くわしたそうですが、それを避けながら、結局、五、六時間かかって兄の遺体を焼いたそうです。あとから父から聞いたのですが、父はその時「鼻歌を歌っていた。」とのことです。ふつう、鼻歌は気分のいい時に出るものでしょうけれど、自分の息子の遺体を父親自らが焼くという作業、そうでもしなくてはとてもやり切れなかったのでしょう。お腹の部分が一番焼けなかったとのことも聞きましたが、骨壺もなかったので、その代わりに味噌を入れる茶色の壺に入れたのですが、焼いた場所の骨に似た小石まで兄の骨と思ってその壺に入れたそうです。
あの日を忘れない
被爆から二、三ヵ月して、「遺体がわかって良かったですね。」とか言われました。「おめでとうございます。」との言葉も言われたことがありますが、「私の方はどこで死んだのかわからない。」と言う人が多かったのです。
ケロイドの残った被爆者、頭髪の抜け落ちたうら若い娘たち...、当時のことは今も忘れられません。
2016年10月1日記